妊娠中に虫歯が悪化しやすい理由とは?予防と治療のポイント
1. 妊娠中に虫歯が進行しやすい理由とは?

ホルモンバランスの変化で虫歯リスクが上昇!
妊娠中の女性は、ホルモンバランスが大きく変化し、口腔内環境にも影響を及ぼします。 特に、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの分泌が増加することで、歯ぐきが腫れやすくなり、歯周病や虫歯のリスクが高まるといわれています。
歯ぐきの腫れや出血が増える
- 妊娠性歯肉炎の発症妊娠中のホルモンの影響で、歯ぐきの血流が増え、炎症を起こしやすくなることがあります。この状態を「妊娠性歯肉炎」と呼び、歯ぐきが腫れることで歯磨きがしにくくなり、プラーク(歯垢)がたまりやすくなるのです。
- 唾液の性質が変化し、虫歯になりやすい環境に妊娠中は、唾液の量や性質が変化し、口の中が酸性に傾きやすくなります。 これにより、歯の再石灰化がうまく行われず、虫歯の進行が早まることがあります。
- 免疫力が低下し、細菌が繁殖しやすくなる妊娠中は、全身の免疫力が低下するため、口腔内の細菌が増殖しやすくなるといわれています。そのため、妊娠前は虫歯がなかった方でも、妊娠を機に急激に虫歯が進行することがあるのです。
つわりで歯磨き不足に?酸で歯が弱くなる危険
つわりがひどい時期は、食事の後に歯を磨こうとしても気分が悪くなり、十分にブラッシングができなくなることがよくあります。また、嘔吐を繰り返すことで胃酸が口の中に広がり、歯の表面(エナメル質)が溶けやすくなるため、虫歯のリスクが一層高まります。
つわりによる口腔内への影響
- 歯磨きができず、プラークがたまりやすくなるつわりがあると、歯ブラシを口に入れるだけで吐き気を感じることもあります。その結果、歯磨きが十分にできず、歯の表面に汚れが残ったままになり、虫歯が進行しやすい状況になってしまいます。
- 胃酸の影響で歯の表面が溶けやすくなるつわりで嘔吐を繰り返すと、胃酸が歯の表面に付着し、エナメル質を溶かしてしまうことがあります。通常、唾液の働きで中和されますが、妊娠中は唾液の分泌量が減ることがあるため、酸が口腔内に長く留まり、虫歯になりやすい環境を作ってしまうのです。
- 甘いものを欲することが多くなる妊娠中は食の好みが変わることがあり、甘いものを食べる頻度が増える方も多いです。しかし、糖分は虫歯の原因菌が好む成分のため、甘いものを頻繁に摂取すると、虫歯の進行が加速することになります。
妊娠中の食生活が虫歯の原因になることも
妊娠中は、栄養バランスを考えながら食事をすることが求められますが、同時に虫歯を予防するための工夫も重要です。特に、間食の回数や食べ物の種類によって、虫歯のリスクが大きく変わるため、注意が必要です。
妊娠中の食習慣と虫歯の関係
- 頻繁な間食が虫歯のリスクを高める妊娠中は、空腹を避けるために間食をする機会が増えることがあります。しかし、食事の回数が増えると、口の中が酸性の状態になりやすく、歯が溶ける時間が長くなるため、虫歯になりやすくなるのです。
- 歯に優しい食べ物を意識する妊娠中の食生活では、カルシウムやビタミンDを含む食品を積極的に摂取し、歯の健康を維持することが重要です。特に、乳製品や小魚、緑黄色野菜は歯や骨を強くする働きがあり、虫歯予防にも役立つため、意識して取り入れると良いでしょう。
- キシリトールを活用する虫歯予防に効果的な方法として、キシリトールガムを取り入れるのも有効です。キシリトールには、虫歯の原因菌の活動を抑え、歯の再石灰化を促す効果があるため、食後に噛む習慣をつけることで、虫歯リスクを軽減できます。
2. 妊娠中の虫歯が母体と赤ちゃんに与える影響

お母さんの虫歯菌が赤ちゃんにうつる!?
妊娠中に進行した虫歯は、お母さん自身の健康に影響を及ぼすだけでなく、生まれてくる赤ちゃんにも悪影響を与える可能性があります。特に、虫歯の原因となる細菌(ミュータンス菌)は母子感染することがあるため、妊娠中からの予防が重要です。
母子感染とは?赤ちゃんに虫歯菌がうつるメカニズム
- 赤ちゃんの口の中には虫歯菌がいない赤ちゃんは、生まれたときには口の中に虫歯菌を持っていません。しかし、母親や周囲の大人の唾液を介して、ミュータンス菌が赤ちゃんの口腔内に移ることがあります。
- スプーンや箸の共有、口移しでの食事、キスなどが感染経路母親が赤ちゃんとスプーンや箸を共有したり、口移しで食べ物を与えたり、キスをしたりすると、虫歯菌が赤ちゃんに感染するリスクが高まります。
- お母さんの虫歯が多いと、赤ちゃんの虫歯リスクが上がる母親の口腔内に虫歯菌が多い場合、赤ちゃんの虫歯リスクが高まります。これは、虫歯菌の量が多いほど、赤ちゃんに感染する確率も高くなるためです。
妊娠中の炎症が早産や低体重児のリスクに
虫歯や歯周病が進行すると、口腔内だけでなく全身の健康にも悪影響を与えることが分かっています。 特に、歯周病に関連する炎症性物質が体内に広がると、早産や低体重児出産のリスクが高まる可能性があるため、注意が必要です。
歯周病が引き起こす全身の炎症反応
- 妊娠中は歯ぐきが腫れやすく、炎症を起こしやすい妊娠中はホルモンバランスの変化により、歯ぐきの血流が増加し、炎症が起こりやすくなります。その結果、歯周病が進行し、細菌が血流に入り込むことで、全身の炎症を引き起こす可能性があります。
- 炎症性物質が胎盤を刺激し、早産のリスクを高める歯周病が悪化すると、炎症性物質(サイトカインやプロスタグランジンなど)が血流に乗り、胎盤に到達することがあります。 これが子宮収縮を引き起こし、早産のリスクを高める要因となることが報告されています。
- 低体重児出産との関連性歯周病や虫歯による炎症が続くと、胎盤の血流が悪くなり、赤ちゃんに十分な栄養が届かなくなることがあります。その結果、赤ちゃんが低体重で生まれるリスクが高まり、出生後の健康にも影響を与える可能性があるのです。
全身の健康にも影響!放置は危険
妊娠中に虫歯を放置すると、口腔内だけでなく、母体全体の健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。虫歯が進行し、神経まで達すると、強い痛みが発生し、睡眠不足やストレスの原因にもなります。
虫歯の痛みがストレスになり、妊娠生活に悪影響を及ぼす
- 妊娠中はストレスが母体や胎児に影響を与える妊娠中は体調の変化が大きく、ちょっとしたストレスでも母体や胎児に影響を与えることがあります。しかし、虫歯の痛みを我慢し続けることで、食欲不振や睡眠不足につながり、母体の健康状態が悪化する可能性があります。
- 妊娠中の免疫力低下で、虫歯が急激に悪化することも妊娠中は免疫力が低下するため、通常であればゆっくり進行する虫歯が、一気に進行してしまうこともあります。
- 妊娠後期に治療を受けにくくなるリスク妊娠中期(5〜7か月頃)は比較的安定した時期であるため、歯科治療を受けやすい時期ですが、妊娠後期に入るとお腹が大きくなり、長時間の診療が負担になるため、治療を控えることが推奨されることもあります。そのため、虫歯が見つかったらできるだけ早めに治療を受けることが大切です。
3. 妊娠時期別!虫歯の進行と治療のベストタイミング

妊娠初期は慎重に!治療を受けるべきタイミング
妊娠初期(0〜4か月)は、赤ちゃんの脳や心臓、神経などの重要な器官が形成される時期です。この時期に強いストレスや薬の影響を受けると、胎児の成長に影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が求められます。 そのため、虫歯があっても、治療のタイミングを慎重に判断する必要があります。
妊娠初期は応急処置が中心
- 本格的な治療よりも痛みを抑える応急処置を優先妊娠初期は、胎児の成長に影響を与えないようにするため、歯科用の薬剤を塗布して炎症を抑えたり、仮の詰め物をするなどの処置が行われます。
- レントゲン撮影や麻酔はできるだけ避けるこの時期は胎児の成長に影響を与える可能性があるため、レントゲン撮影や麻酔の使用は必要最低限にとどめます。ただし、歯科用レントゲンは放射線量が少なく、防護エプロンを着用することでリスクを最小限に抑えられます。
- つわりで歯磨きがしにくい時期は、セルフケアを工夫するうがい薬を活用したり、歯ブラシのヘッドが小さいものを使うなど、工夫しながらケアを続けることが大切です。
妊娠中期がチャンス!虫歯を悪化させない対策
妊娠中期(5〜7か月)は、妊娠が比較的安定し、体調も落ち着いてくる時期です。このため、虫歯の治療を行う最適なタイミングとされています。
本格的な虫歯治療が可能になる
- 胎盤が完成し、赤ちゃんが安定して成長する時期麻酔を使用した治療やレントゲン撮影も、必要に応じて行うことが可能になります。ただし、麻酔の使用は最小限に抑え、できるだけ母体への負担が少ない方法が選択されます。
- 早めの治療で虫歯の進行を防ぐ妊娠中期に治療を行うことで、妊娠後期や出産後に虫歯が悪化するリスクを軽減できます。
- 妊婦歯科検診を活用し、口腔内の状態をチェック多くの自治体では、妊婦歯科検診を無料または低価格で受けられる制度があるため、この機会を活用して口腔内の状態を確認しておくことが重要です。
妊娠後期は負担が大きい?応急処置で対応する方法
妊娠後期(8〜10か月)は、お腹が大きくなり、歯科診療を受ける際の姿勢が負担になりやすい時期です。そのため、この時期の治療はできるだけ最小限に抑え、応急処置が中心となります。
妊娠後期における歯科治療の注意点
- 仰向けの診療姿勢が辛くなる長時間横になるとお腹の重みで血流が悪くなり、体調を崩しやすくなります。特に、低血圧症の方は注意が必要であり、治療を受ける際には、体勢をこまめに調整しながら診療を進めることが推奨されます。
- 急を要する場合のみ最小限の処置を行う虫歯の痛みがひどくなった場合、痛みを抑えるための応急処置を行い、本格的な治療は産後に行うことが一般的です。
- 産後の治療計画を立てる妊娠後期に本格的な治療が難しい場合は、産後に治療を受けるためのスケジュールを立てておくことが大切です。
4. 妊娠中の虫歯を防ぐセルフケアのポイント

つわりでもできる!歯磨きの工夫
妊娠中のつわりが原因で、歯磨きが思うようにできない方も多くいます。しかし、歯磨きを怠ると虫歯のリスクが急激に高まり、口腔環境が悪化してしまうため、無理のない範囲で適切なセルフケアを続けることが重要です。
つわり中の歯磨きの工夫
- 歯ブラシのサイズを小さくし、磨きやすくするヘッドの小さい歯ブラシを使うと奥歯まで磨きやすくなり、嘔吐反射を軽減できます。
- 歯磨き粉を無理に使わず、水や洗口液でうがいをするミントの強い香りや泡立ちが苦手な場合は、低刺激の歯磨き粉や、無理に歯磨き粉を使用せず水だけで磨くのも一つの方法です。
- 寝る前の歯磨きを最優先に!短時間でも丁寧に磨くつわりがひどく、毎食後の歯磨きが難しい場合は、最低でも寝る前の歯磨きを徹底することが大切です。
フッ素や洗口液で虫歯予防を強化
妊娠中は、ホルモンバランスの変化やつわりの影響で虫歯が進行しやすいため、フッ素や洗口液を活用して虫歯予防を強化することが効果的です。
フッ素を活用したケア
- フッ素入り歯磨き粉を活用し、歯の再石灰化を促すフッ素には、歯のエナメル質を強化し、虫歯の進行を抑える働きがあります。
- フッ素配合の洗口液で手軽にケアつわりで歯磨きが難しいときは、フッ素配合の洗口液を活用するのも効果的です。
- 妊娠中でも使えるフッ素製品を選ぶ歯科用のフッ素は安全性が確認されており、妊娠中でも問題なく使用できます。
間食のコントロールで虫歯を予防する方法
妊娠中は、ホルモンの影響で食の好みが変わったり、空腹を感じやすくなったりするため、間食の回数が増えることがあります。しかし、間食の回数が増えると、口腔内が酸性になりやすく、虫歯のリスクが高まるため、食べ方に注意が必要です。
間食を管理するポイント
- 間食の回数を減らし、時間を決めて食べるダラダラと間食を続けると、歯が酸にさらされる時間が長くなり、虫歯の進行を助長してしまいます。
- 糖分の多い食べ物・飲み物を控える砂糖を多く含むお菓子やジュースは、虫歯菌のエサになりやすいため注意が必要です。
- カルシウムやビタミンDを積極的に摂取する牛乳やヨーグルト、小魚、大豆製品などのカルシウムが豊富な食品を意識して摂ることで、歯の再石灰化を促し、虫歯の進行を防ぐことができます。
5. 妊娠中でも受けられる安全な虫歯治療

妊娠中にできる治療と注意点
妊娠中の歯科治療は、安全性が気になるところですが、適切なタイミングと方法を選べば、母体や胎児に負担をかけずに虫歯治療を受けることが可能です。特に、妊娠中期(5〜7か月)が最も安定している時期とされ、この時期に治療を進めるのが推奨されます。
虫歯の進行度に応じた治療を選択
- 初期の虫歯 → フッ素塗布や歯のクリーニングで進行を抑える
- 中程度の虫歯 → 詰め物や被せ物をする治療が必要
- 重度の虫歯 → 応急処置を行い、産後に本格的な治療を計画
痛みがある場合の対処法
- 妊娠中の強い虫歯の痛みは、母体にストレスを与え、胎児にも影響を与える可能性があるため、早めの治療が推奨されます。
- 妊娠後期(8〜10か月)は、治療の負担を避けるため、基本的には応急処置が中心となります。
レントゲン・麻酔は安全?正しい知識を解説
歯科用レントゲンの安全性
- 歯科のレントゲンは放射線量が低く、防護用のエプロンを着用することで胎児への影響を最小限に抑えられます。
- 妊娠初期のレントゲン撮影は可能な限り避け、必要な場合のみ行います。
局所麻酔の安全性
- 歯科治療で使用される局所麻酔(リドカイン)は、胎盤を通過しにくく、通常の使用量であれば胎児への影響はほとんどありません。
- 痛みを我慢するよりも、適切な麻酔を使用したほうが母体のストレスを軽減できます。
妊娠中に使用できる薬の注意点
- 妊娠中でも安全に使用できる薬(例:アセトアミノフェン(カロナール))が処方されます。
- 自己判断で服用を中断せず、必ず歯科医師の指示に従いましょう。
妊娠中に避けたほうがよい歯科処置とは?
抜歯や大掛かりな外科処置
- 親知らずの抜歯やインプラント手術は、母体に負担がかかるため、通常は産後に延期されます。
- 感染リスクや強い痛みがある場合は、歯科医師と相談のうえ、安全な範囲で処置が行われます。
強い薬剤を使用するホワイトニング
- ホワイトニングに使用される薬剤の胎児への影響が不明なため、妊娠中の施術は推奨されていません。
歯列矯正や審美歯科治療
- 矯正装置の調整による痛みや違和感、ストレスが母体に影響を与える可能性があるため、出産後に開始するのが理想的です。
- セラミック治療などの審美歯科治療は妊娠中でも可能ですが、体調が安定しない時期は避けたほうが良いでしょう。
6. 妊娠中の歯科検診が大切な理由
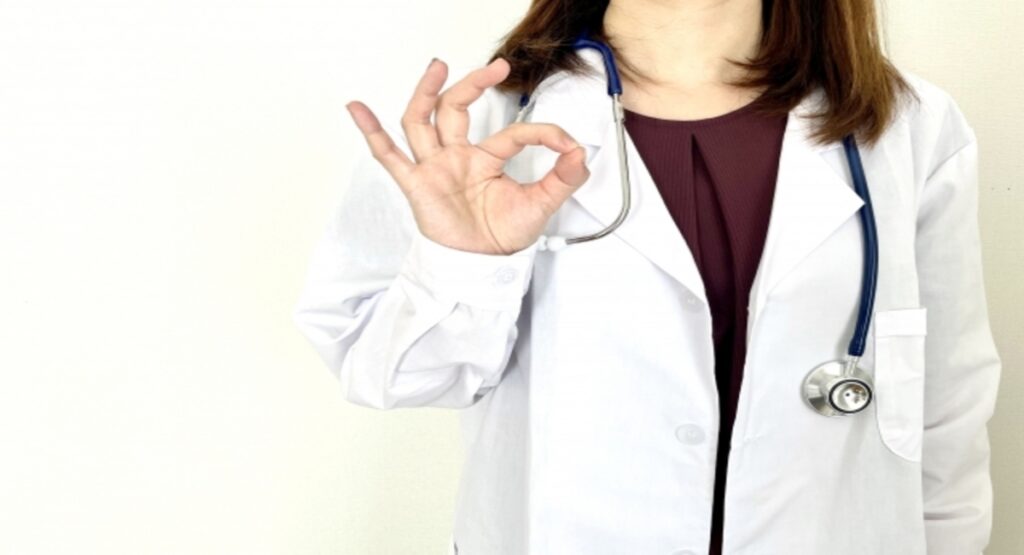
妊婦歯科検診で虫歯を早期発見!
妊娠中はホルモンバランスの変化や食生活の変化によって、虫歯や歯周病のリスクが大幅に上がることが知られています。そのため、定期的な歯科検診を受けることで、虫歯や歯ぐきの異常を早期に発見し、必要なケアを行うことが重要です。
妊娠中は虫歯の進行が早くなる
- ホルモンバランスの変化により、唾液の分泌量が減少し、口腔内の細菌が増殖しやすくなる。
- つわりによる歯磨き不足や糖分の摂取増加で、虫歯が進行しやすい環境が整ってしまう。
妊娠中の口腔トラブルは母体や赤ちゃんにも影響を及ぼす
- 虫歯や歯周病が悪化すると、炎症が全身に影響し、早産や低体重児出産のリスクが高まる可能性がある。
- 歯科検診を受けることで、口腔内の異常を早期に発見し、妊娠期間中のリスクを最小限に抑える。
妊娠中の治療はタイミングが限られるため、早めの検診が大切
- 妊娠中期(5〜7か月)が最も治療に適した時期とされる。
- それ以降は体調や胎児への影響を考慮し、治療の選択肢が限られてしまうこともある。
- 早めに歯科検診を受けることで、虫歯や歯ぐきの問題を事前に把握し、最適なタイミングで治療を進められる。
妊娠性歯肉炎の予防にもつながる
妊娠中のホルモンバランスの変化により、歯ぐきが炎症を起こしやすくなる「妊娠性歯肉炎」が発症しやすくなります。これは、妊娠中に女性ホルモンのエストロゲンやプロゲステロンが増加し、歯ぐきの血流が増えることで、細菌に対する抵抗力が低下するためです。
妊娠性歯肉炎とは?
- 歯ぐきが赤く腫れ、出血しやすくなる歯肉炎の一種。
- 妊娠前には問題がなかった方でも、妊娠中に急に歯ぐきが腫れたり、出血しやすくなることがある。
妊娠性歯肉炎を放置するとどうなる?
- 炎症が進行して歯周病へと発展する可能性がある。
- 歯周病が悪化すると、炎症性物質が血流に入り込み、子宮の収縮を促進し、早産や低体重児出産のリスクを高める。
定期的な歯科検診で歯ぐきの健康をチェック
- 妊娠性歯肉炎は、定期的な歯科検診と適切なクリーニングを受けることで予防できる。
- 歯ぐきの腫れや出血が気になる場合は、プロによるケアを受けることで、炎症を抑え、健康な口腔環境を維持できる。
歯科クリーニングで虫歯リスクを最小限に
妊娠中は、セルフケアだけでは防ぎきれない汚れやプラーク(歯垢)が蓄積しやすくなるため、定期的な歯科クリーニングを受けることで、虫歯や歯周病のリスクを最小限に抑えることができます。
プロによるクリーニングで歯石を除去
- 歯科医院でのクリーニングでは、自分では取り除けない歯石をしっかりと除去できる。
- 歯石は細菌の温床となりやすく、虫歯や歯周病を悪化させる原因となるため、定期的に除去することが大切。
フッ素塗布で虫歯を予防
- 歯科医院では、妊娠中でも安全に受けられるフッ素塗布を行い、歯の再石灰化を促して虫歯を予防できる。
- フッ素は歯の表面を強化し、酸に対する耐性を高める働きがあるため、虫歯の進行を防ぐ効果が期待できる。
口腔環境を整えるアドバイスを受ける
- 妊娠中の口腔ケアのポイントや、つわり時の歯磨きのコツなどについて、専門的なアドバイスを受けられる。
- 妊娠中の口腔環境は通常とは異なるため、プロのアドバイスを活用しながら適切なケアを続けることが重要。
7. 妊娠中の歯科治療に関する疑問と不安

麻酔は大丈夫?赤ちゃんへの影響は?
妊娠中に歯科治療を受ける際、「麻酔を使っても赤ちゃんに影響はないのか?」と不安に思う方が多いでしょう。しかし、歯科で使用される局所麻酔は、適切な量であれば胎児に悪影響を与えることはほとんどないとされています。
歯科用の局所麻酔は胎盤を通過しにくい
- 歯科で一般的に使用されるリドカイン(キシロカイン)は、胎盤をほとんど通過しないため、赤ちゃんへの影響は最小限。
- 痛みを我慢して治療を受けるよりも、必要に応じて麻酔を使用し、安全に治療を進める方が望ましい。
妊娠中に避けたほうがよい麻酔の種類
- 一般的な局所麻酔は安全だが、エピネフリン(血管収縮剤)が含まれる麻酔薬は慎重に使用する必要がある。
- 妊婦向けに血管収縮剤を含まない麻酔薬を使用するケースが多いので、事前に相談すると安心。
妊娠中の麻酔の安全な使用方法
- 必要最小限の麻酔を使用し、治療後はできるだけ早めに効果が切れるよう調整される。
- 治療中の体勢を工夫し、母体に負担がかからないよう配慮することが大切。
歯の痛みがあるとき、受診すべきタイミング
妊娠中に虫歯や歯の痛みを感じた場合、「治療を受けるべきか、産後まで待つべきか?」と悩む方もいるでしょう。しかし、痛みが強い場合や、虫歯の進行が見られる場合は、早めに受診することが重要です。
軽度の痛みなら、妊娠中期(5〜7か月)に治療を
- 妊娠中期は母体の状態が安定しやすく、治療を受けるのに適したタイミング。
- 軽度の虫歯であれば、この時期に治療を済ませておくことで、産後に悪化するリスクを防げる。
妊娠後期は緊急性が高い場合のみ処置を行う
- 妊娠後期(8〜10か月)は、お腹が大きくなり、長時間の治療が母体に負担をかける。
- 緊急性の高い場合のみ応急処置を行い、出産後に本格的な治療を行うケースが多い。
放置すると痛みが悪化する可能性がある
- 虫歯の痛みを我慢していると、炎症が進行し、痛みが激しくなるだけでなく、睡眠不足や食欲不振を引き起こすことも。
- 母体や胎児の健康にも影響を与える可能性があるため、痛みを感じたら早めに歯科医院を受診することが大切。
妊娠中に治療をせず放置するとどうなる?
妊娠中は、「痛みがひどくなければ、産後に治療すればいい」と考える方もいるかもしれません。しかし、虫歯や歯周病を放置すると、母体や胎児にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
炎症が全身に広がるリスクがある
- 進行した虫歯を放置すると、歯の根元(根尖)に炎症が広がり、膿がたまる「根尖性歯周炎」を引き起こすことがある。
- 悪化すると、細菌が血流に入り込み、全身に影響を及ぼすこともあるため、早めの治療が必要。
妊娠中のホルモン変化で虫歯が急激に進行することも
- 妊娠中は免疫力が低下し、ホルモンバランスが変化することで、通常よりも虫歯の進行が早くなることがある。
- 妊娠性歯肉炎を併発している場合、歯ぐきの炎症が悪化し、歯を支える組織が弱くなるリスクもある。
出産後は治療の時間がとれなくなる可能性がある
- 産後は赤ちゃんのお世話に追われ、自分のための時間を確保するのが難しくなることが多い。
- 虫歯や歯の痛みを抱えたまま育児をすることになり、ストレスが増えてしまうこともある。
- 出産後に治療を受けるのが難しくなることを考えると、妊娠中にできるだけ治療を済ませておくのが理想的。
8. 出産後に影響する?妊娠中の虫歯リスク

産後は忙しくて歯医者に行けない!?
出産後は、赤ちゃんのお世話で日々の生活が大きく変わり、自分の体のケアを後回しにしてしまうことが多くなります。そのため、妊娠中に進行した虫歯を放置したまま出産を迎えると、産後に治療の時間を確保するのが難しくなり、さらに症状が悪化してしまうリスクがあります。
育児に追われて歯科受診の時間が取れなくなる
- 赤ちゃんが生まれると、授乳やおむつ替え、寝かしつけなどで1日があっという間に過ぎてしまい、歯科医院に行く余裕がないケースが多い。
虫歯が悪化しやすい環境になる
- 産後は睡眠不足やホルモンバランスの変化で免疫力が低下し、虫歯の進行が早まる可能性がある。
授乳中の食生活も影響する
- 授乳中はエネルギー消費が激しく、間食の回数が増えることで虫歯リスクがさらに高まる可能性がある。
- 授乳によって母体のカルシウムが消費されるため、歯の再石灰化が十分に行われず、虫歯が悪化しやすくなる。
授乳期の栄養バランスが歯の健康を左右する
出産後の母体は、赤ちゃんへの授乳によって栄養を消費しやすくなり、歯や骨の健康にも影響を与えます。そのため、適切な栄養を摂取しながら、口腔ケアにも気を配ることが重要です。
カルシウム不足が歯に影響を与える
- 授乳によって母体のカルシウムが失われると、歯や骨の健康が損なわれる可能性が高まる。
- カルシウム不足は歯のエナメル質を弱くし、虫歯になりやすい状態を引き起こすため、積極的に摂取することが重要。
ビタミンDの摂取でカルシウムの吸収を促進
- カルシウムを効率よく体内に吸収するためには、ビタミンDの摂取が欠かせない。
- ビタミンDは、魚やきのこ類に多く含まれ、日光を浴びることで体内でも生成される。
糖分の摂取を控え、虫歯リスクを軽減
- 授乳中は甘いものを食べたくなることがあるが、糖分の摂取量が増えると虫歯のリスクが高まる。
- 間食の回数を減らし、砂糖を控えた食品を選ぶことが歯の健康を守るポイントになる。
虫歯を放置すると子どもの口腔環境にも影響が
母親の口腔環境は、赤ちゃんの口腔内にも影響を及ぼすことが知られています。特に、虫歯の原因となるミュータンス菌は、母子感染する可能性があるため、産後の虫歯ケアが重要です。
母子感染のリスクを高める
- 生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には、虫歯菌(ミュータンス菌)が存在しない。
- 母親が虫歯を放置したままだと、唾液を介して赤ちゃんに菌がうつるリスクが高くなる。
- スプーンの共有やキスなどで、母親の虫歯菌が赤ちゃんの口に入り込む可能性がある。
子どもの歯の生え方や健康にも影響
- 母親の口腔環境が悪いと、赤ちゃんの歯の生え方にも影響を与える可能性がある。
- 歯周病の炎症が長期間続くと、血流を通じて胎児の成長にも影響を及ぼし、将来的に歯並びが悪くなる可能性がある。
子どもの虫歯予防のためにも、母親の口腔ケアが重要
- 赤ちゃんの虫歯予防には、母親が適切な口腔ケアを行い、虫歯菌のリスクを減らすことが大切。
- 母親が虫歯を治療し、口腔内の細菌数を減らすことで、赤ちゃんの虫歯リスクを大幅に軽減できる。
9. 家族みんなでできる!妊娠中の虫歯予防

パートナーも一緒に!家族の口腔ケアが大切
妊娠中の虫歯予防は、妊婦さん自身が気をつけるだけでなく、家族全体で取り組むことが重要です。特に、パートナーや家族が口腔内の健康を意識することで、妊婦さんの虫歯リスクを減らし、赤ちゃんの未来の健康にもつながります。
妊娠中の感染リスクを下げるために、家族も口腔ケアを強化
- 妊娠中はホルモンバランスの変化により、虫歯菌や歯周病菌が増えやすくなる。
- 家族が虫歯や歯周病を持っていると、食器の共有やキスなどで妊婦さんに細菌が感染する可能性があるため、家族全員が口腔ケアを徹底することが大切。
パートナーが定期的に歯科検診を受けることが妊婦の健康にもつながる
- 妊婦さんだけでなく、パートナーや子どもも一緒に歯科医院を受診することで、家族全体の口腔環境を整える。
- パートナーが虫歯や歯周病を持っている場合は、早めに治療を受けることで、妊婦さんへの感染リスクを軽減できる。
家族みんなで同じ口腔ケア習慣を実践する
- 寝る前の歯磨きを徹底する。
- フッ素入りの歯磨き粉を使用する。
- キシリトールガムを噛む習慣をつける。
赤ちゃんのために!両親の虫歯菌を減らす
生まれたばかりの赤ちゃんの口の中には、虫歯菌(ミュータンス菌)が存在しません。しかし、親や家族の唾液を介して感染することで、虫歯のリスクが高まるため、家族全員の虫歯菌を減らすことが重要です。
スプーンや箸の共有を避ける
- 家族の唾液が赤ちゃんの口に入らないようにする。
- スプーンや箸の共有を避ける、食べ物の口移しをしない。
キシリトールの活用で虫歯菌の繁殖を抑える
- キシリトールには、虫歯菌の働きを抑制し、口腔内の細菌バランスを整える効果がある。
- 妊娠中や授乳中でも安心して摂取できるため、キシリトールガムを噛む習慣をつけるとよい。
親の口腔環境を整えることが赤ちゃんの健康につながる
- 母親だけでなく、父親や同居している家族も虫歯予防に取り組むことで、赤ちゃんの口腔環境を守る。
生活習慣を見直して家族全員で虫歯予防
妊娠中の虫歯予防は、日々の生活習慣を見直すことから始まります。家族みんなで健康的な食生活や正しい歯磨き習慣を実践することで、妊婦さんの虫歯リスクを減らし、赤ちゃんの未来の健康にも良い影響を与えます。
砂糖の摂取量を控え、虫歯リスクを減らす
- 妊娠中は甘いものを食べたくなることがあるが、砂糖の摂取量が増えると虫歯菌が増殖しやすくなる。
- 家族全員で甘いものの摂取を控えることが理想的。
- 食後すぐに歯を磨く習慣をつけることで、虫歯のリスクを大幅に減らせる。
歯に優しい食品を取り入れる
- カルシウムやビタミンDが豊富な食品(乳製品・小魚・豆腐など)を積極的に摂取することで、歯の再石灰化を促し、虫歯予防につながる。
寝る前の口腔ケアを徹底する
- 寝る前は唾液の分泌が少なくなるため、虫歯菌が活発になりやすい時間帯。
- 家族全員が寝る前にしっかり歯を磨く習慣をつけることで、口腔内の細菌の繁殖を抑えることができる。
10. 妊娠中の虫歯予防と治療で安心して出産を迎えよう

妊娠中だからこそ定期検診が重要!
妊娠中の口腔環境は、ホルモンバランスの変化や食生活の影響で、虫歯や歯周病が進行しやすくなります。そのため、妊娠中こそ定期的な歯科検診を受け、虫歯や歯ぐきの異常を早期に発見することが重要です。
妊娠期ごとに適した歯科検診を受ける
- 妊娠初期:口腔内のチェックとセルフケアのアドバイスが中心
- 妊娠中期:虫歯や歯周病の治療を積極的に行う
- 妊娠後期:お腹が大きくなるため、応急処置が中心
妊婦歯科検診を活用する
- 多くの自治体では妊婦向けの無料歯科検診を実施
- 専門的なチェックを受けることで、妊娠中のリスクを軽減
妊娠中の歯科検診でチェックするポイント
- 虫歯の有無
- 歯ぐきの健康状態
- 歯石の有無
- 噛み合わせの異常
虫歯があるならタイミングを見て適切な治療を
妊娠中期(5〜7か月)が治療に適した時期
- 母体の状態が安定しやすい
- 麻酔を使用した治療や、詰め物・被せ物の処置が可能
- 軽度の虫歯はこの時期に治療を済ませるのが理想
妊娠後期は応急処置が中心
- お腹が大きくなり、仰向けの治療が負担になる
- 痛みが強い場合のみ応急処置を行い、本格的な治療は産後に持ち越す
- 仮詰めなどで虫歯の進行を防ぐ
産後の治療スケジュールを考える
- 産後は育児に追われるため、治療を先延ばしにしない
- 妊娠中に治療を済ませるのが理想
- 産後に治療を行う場合は、計画的に受診する
健康な歯で出産し、赤ちゃんの未来を守る
母子感染を防ぐために、妊娠中から虫歯菌を減らす
- 赤ちゃんは生まれたときには虫歯菌を持っていない
- 母親や家族の唾液を介して虫歯菌が感染する可能性がある
- 妊娠中から虫歯や歯周病の治療を行い、口腔内の細菌量を減らす
産後は自分の歯のケアを怠らないことが大切
- 育児に追われると自分の口腔ケアを後回しにしがち
- 母親の虫歯や歯周病が赤ちゃんに感染するリスクが高まる
- 母子感染を防ぐためにも、産後も定期的な歯科検診を受ける
赤ちゃんのためにも、妊娠中からできるケアを徹底する
- 妊娠中の定期検診を受ける
- 歯科医師のアドバイスを参考にセルフケアを徹底する
- 食生活を見直し、虫歯リスクを抑える
監修:愛育クリニック麻布歯科ユニット
所在地〒:東京都港区南麻布5丁目6-8 総合母子保健センター愛育クリニック
電話番号☎:03-3473-8243
*監修者
愛育クリニック麻布歯科ユニット
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会
カテゴリー:コラム 投稿日:2025年3月31日

