妊婦さんのための歯科検診の必要性と注意点を徹底解説!
1. 妊婦さんに歯科検診が必要な理由とは?
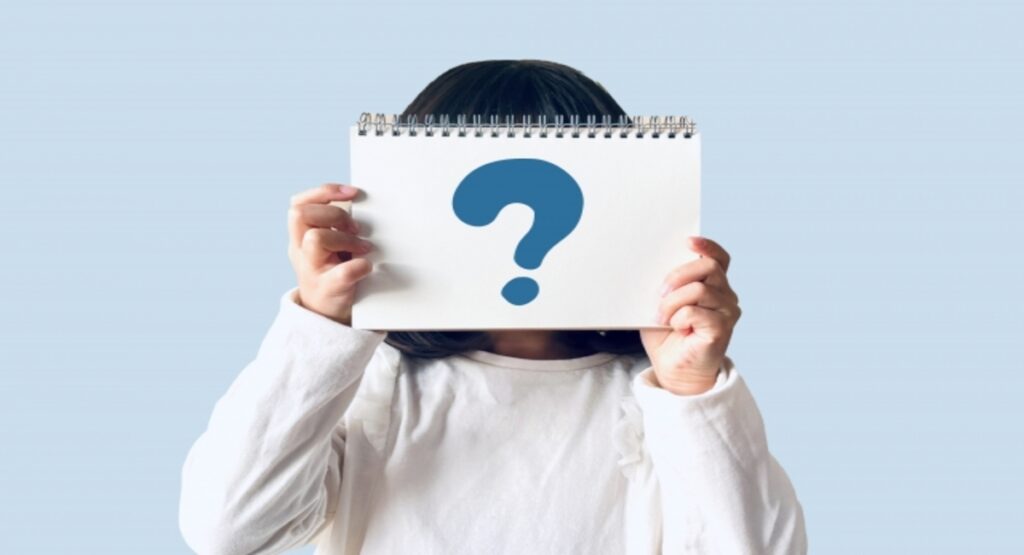
・妊娠中のホルモンバランスの変化が口腔内に与える影響
妊娠すると、体内のホルモンバランスが大きく変化します。特に、エストロゲンとプロゲステロンといった女性ホルモンの分泌が増加し、これが歯ぐきの血流や組織に影響を与えます。血管が拡張し、歯ぐきが腫れやすくなるため、普段と同じように歯磨きをしていても炎症を起こしやすい状態になります。
また、妊娠中は免疫機能が変化するため、口腔内の細菌への抵抗力が低下しがちです。結果として、歯周病やむし歯のリスクが上がるだけでなく、口臭が気になりやすくなる方も増えます。こうした影響を抑えるためにも、妊娠中の定期的な歯科検診が推奨されるのです。
・妊婦さんが歯周病になりやすい理由
妊娠中は、妊娠性歯肉炎と呼ばれる特有の歯ぐきの炎症が起こりやすくなります。この状態は、妊婦さんの約半数に見られると言われており、特に妊娠初期から中期にかけて顕著になります。これは、ホルモンの変化によって歯ぐきが敏感になり、少しの歯垢や歯石の蓄積でも炎症を起こしやすくなるためです。
加えて、つわりによる歯磨き不足も関係しています。つわりがひどいと、歯ブラシを口に入れるだけで気持ち悪くなってしまい、十分にブラッシングができなくなることがあります。その結果、歯垢や歯石が増え、歯周病が進行しやすくなるのです。
妊娠中に歯周病が悪化すると、口腔内の細菌が血流に入り込み、全身の炎症を引き起こす可能性があります。これが妊娠高血圧症候群や早産・低体重児出産のリスクを高めることが、近年の研究で明らかになっています。そのため、妊婦さんにとっての歯科検診は、単に口腔内の健康を守るだけでなく、赤ちゃんの健康にも関わる大切なケアなのです。
・赤ちゃんへの影響と妊娠期の口腔ケアの重要性
歯周病にかかっている妊婦さんは、早産や低体重児出産のリスクが高くなることが指摘されています。これは、歯周病菌が血流を介して胎盤に影響を及ぼし、子宮の収縮を促す可能性があるためです。通常、妊娠37週未満で生まれた赤ちゃんは、健康リスクが高まるため、妊娠中の歯の健康管理が重要視されています。
また、妊娠中のむし歯菌が赤ちゃんに影響を及ぼすこともあります。出産後、赤ちゃんが母親の唾液を通じてむし歯菌に感染するケースが多いため、妊娠中からしっかりとむし歯を予防することで、赤ちゃんの歯の健康を守ることにもつながります。
妊娠期にしっかりと歯科検診を受け、適切なケアを行うことで、母子ともに健康な口腔環境を維持できるのです。まずは、妊娠中期の安定期に一度、歯科医院で検診を受けることをおすすめします。
2. 妊娠中に起こりやすい歯や歯ぐきのトラブル
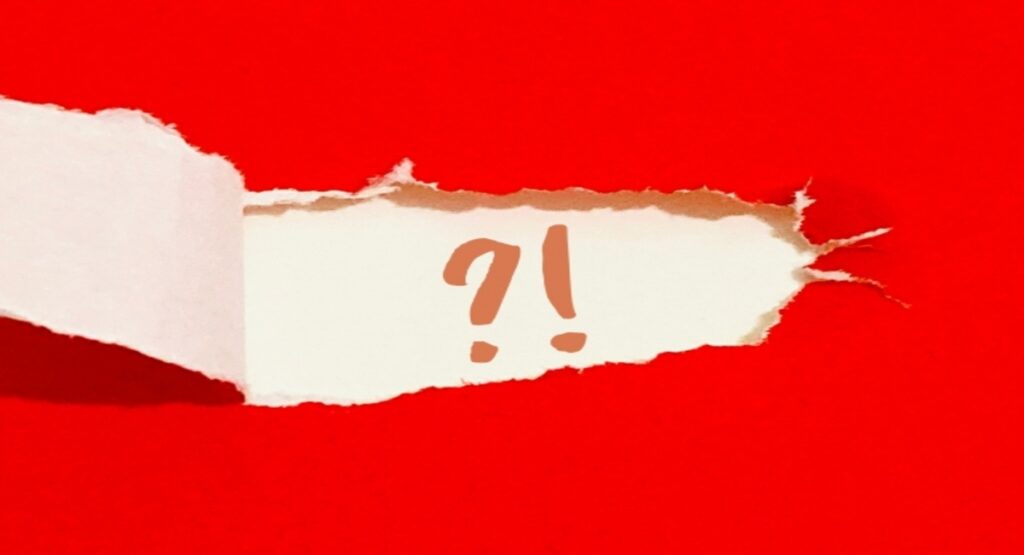
・妊娠性歯肉炎とは?妊婦の約半数が経験する歯ぐきの腫れ
妊娠中に多くの女性が経験するのが 妊娠性歯肉炎 です。妊娠中に増加するエストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンは、歯ぐきの血管を拡張させ、炎症を引き起こしやすくします。そのため、普段は問題なく歯磨きできていた人でも、妊娠中に歯ぐきが腫れたり、出血しやすくなったりする ことがあります。
この状態を放置すると、炎症が悪化し、歯ぐきが赤く腫れて痛みを伴うようになります。さらに、進行すると歯周病につながる可能性 もあります。特に、妊娠中期から後期にかけて歯ぐきの腫れが悪化することが多いため、早めに予防策をとることが重要です。
妊娠性歯肉炎を防ぐためには、正しいブラッシングとデンタルフロスの活用 が効果的です。また、妊娠中期に歯科検診を受け、歯石除去やクリーニングを行うことで、炎症を抑えやすくなります。
・つわりによる歯磨き不足とむし歯リスクの増加
妊娠初期に多くの妊婦さんが経験する つわり は、口腔ケアの大きな妨げになります。つわりがあると、歯ブラシを口に入れるだけで吐き気を感じる ことがあり、歯磨きを避けてしまう人も少なくありません。しかし、これによって磨き残しが増えると、むし歯や歯周病のリスクが一気に高まります。
また、つわりの影響で、酸っぱいものや炭酸飲料、甘い食べ物を口にする機会が増える 人も多いでしょう。酸性の飲食物が増えると、歯の表面が溶けやすくなり、むし歯になりやすい環境 が作られてしまいます。特に、嘔吐を伴うつわりがある場合、胃酸が口の中に逆流し、歯のエナメル質が酸で弱くなってしまうこともあります。
つわりが原因で歯磨きが難しい場合は、以下のような工夫を取り入れるとよいでしょう。
・歯ブラシを小さいヘッドのものに変える(口の奥に入れたときの不快感を軽減)
・ミント系の歯磨き粉を避け、無香料や低刺激のものを使用する
・食後すぐの歯磨きを避け、少し時間を置いてから行う
・うがいだけでもこまめに行い、口腔内を清潔に保つ
むし歯が進行すると、妊娠中に治療が必要になることもあります。つわりの期間が終わったら、早めに歯科検診を受けて、むし歯の有無を確認することをおすすめします。
・ホルモンの影響で口内環境が悪化しやすい理由
妊娠中のホルモンバランスの変化は、歯ぐきだけでなく、口の中の唾液の質や量 にも影響を与えます。唾液には口内の汚れを洗い流す働きがありますが、妊娠中は唾液の分泌量が減ることがあり、細菌が増殖しやすい環境 になってしまいます。特に、妊娠後期にかけて口の中が乾燥しやすくなるため、口臭が強くなる と感じる人もいます。
また、妊娠中は免疫機能も変化するため、細菌に対する抵抗力が低下 しやすくなります。通常なら問題にならない程度の細菌でも、妊娠中は口内トラブルを引き起こしやすくなるのです。
このような変化を防ぐために、以下のような対策を取り入れましょう。
・こまめに水分補給をして口の中の乾燥を防ぐ
・キシリトールガムを噛んで唾液の分泌を促す
・ノンアルコールのマウスウォッシュを活用する
また、妊娠中に歯の違和感や痛みを感じたら、できるだけ早めに歯科医院を受診することが大切 です。妊娠中の体調の変化に合わせて、無理のない範囲で口腔ケアを続けていきましょう。
3. 妊娠中の歯周病が及ぼす母体と赤ちゃんへのリスク

・歯周病が早産や低体重児出産のリスクを高める可能性
妊娠中に歯周病を発症または悪化させてしまうと、早産や低体重児の出産リスクが高まる ことが報告されています。
これは、歯周病によって増殖した細菌が歯ぐきの血管に侵入し、血流を介して全身に影響を及ぼすためです。
具体的には、歯周病菌が子宮の収縮を促す炎症性物質を分泌する ことで、早産のリスクを高める可能性があります。
通常、出産は37週以降が理想的とされていますが、歯周病がある妊婦さんは妊娠37週未満で出産する確率が高い ことが分かっています。
また、低体重児として生まれた赤ちゃんは、免疫機能が未発達であるため、感染症や発達の遅れなどのリスクが高まることも指摘されています。
そのため、妊娠中の歯科検診は、母体の健康を守るだけでなく、赤ちゃんの健やかな成長をサポートするためにも非常に重要です。
・歯周病菌が血流を通じて全身に影響を与える仕組み
歯周病は、単なる口腔内の病気ではなく、全身疾患と深い関係 を持っています。
歯周病が進行すると、炎症が慢性化し、歯ぐきの毛細血管を通じて細菌や毒素が血流に乗る ことがあります。
これにより、体のさまざまな部位に炎症が広がることが考えられます。
妊娠中はホルモンバランスが大きく変化し、免疫力が低下しやすくなる ため、歯周病が悪化しやすい状態になります。
さらに、歯周病が血流を通じて全身に炎症を引き起こすと、母体の免疫機能が過剰に働き、胎児の発育にも悪影響を与える可能性があるのです。
また、妊娠糖尿病のリスクも指摘されています。
近年の研究では、歯周病が進行すると血糖値のコントロールが難しくなり、妊娠糖尿病を発症するリスクが高まる ことが分かっています。
妊娠糖尿病は母体だけでなく、胎児にも影響を与えるため、注意が必要です。
・妊娠中でも安全に受けられる歯周病予防策とは?
歯周病のリスクを軽減するためには、妊娠中でも適切な予防策を講じることが大切です。
歯周病予防には、日常のセルフケアと歯科医院での定期的なチェックが不可欠 です。
妊娠中に歯科検診を受ける際は、安定期(妊娠5〜8ヶ月頃)が最も適していると言われています。
特に、歯ぐきの炎症や出血が気になる場合は、早めにスケーリング(歯石除去)を受ける ことで、歯周病の進行を防ぐことができます。
また、妊娠期はつわりやホルモンバランスの変化によって、通常よりも口腔内のケアが難しくなることがあります。
そのため、歯科医院でプロフェッショナルクリーニング(PMTC)を受けることで、普段のセルフケアでは落としきれない汚れを徹底的に除去 し、歯周病のリスクを最小限に抑えることができます。
さらに、セルフケアのポイントとして、以下の点を意識すると良いでしょう。
・フロスや歯間ブラシを使用し、歯と歯の間のプラークをしっかり取り除く
・妊娠中でも使用可能な殺菌成分入りの歯磨き粉を活用する
・食生活を見直し、歯ぐきを健康に保つ栄養素(ビタミンC・カルシウム)を積極的に摂取する
4. 妊娠期の歯科検診を受けるベストなタイミング

・妊娠初期・中期・後期の歯科検診の注意点
妊娠期を「初期(0〜4ヶ月)」「中期(5〜8ヶ月)」「後期(9ヶ月以降)」の3つに分け、それぞれの時期における歯科検診の受診について見ていきましょう。
・妊娠初期(0〜4ヶ月)
妊娠初期はつわりが強く出る時期であり、体調が不安定になりやすい時期です。特に、歯科治療中の仰向けの姿勢がつらく感じたり、口を開けるだけで吐き気を催すこともあります。
そのため、歯科検診を受けるのは可能な限り体調の良いタイミングを選ぶことが大切です。
また、この時期は赤ちゃんの重要な器官が形成される発育の大切な時期でもあるため、できるだけ麻酔やレントゲン撮影を避けることが推奨されます。
・妊娠中期(5〜8ヶ月)
妊娠中期は「安定期」と呼ばれ、体調が比較的落ち着いてくるため、歯科検診を受けるのに最も適したタイミングです。
この時期には歯科治療も比較的安全に行うことができ、むし歯や歯周病の治療が必要であれば、できるだけこの時期に終わらせるのが理想です。
また、妊娠中期は妊娠性歯肉炎が悪化しやすい時期でもあるため、スケーリング(歯石除去)やPMTC(プロフェッショナルクリーニング)を受けるのもおすすめです。
・妊娠後期(9ヶ月以降)
妊娠後期になると、お腹が大きくなり、仰向けの姿勢がつらくなるため、長時間の治療を受けるのは難しくなります。
また、出産が近づくと体調の変化が起こりやすくなるため、この時期の歯科検診は短時間で済む検診や軽いクリーニング程度にとどめるのが望ましいでしょう。
もしも治療が必要な場合は、産後に改めて受診することを検討するのが一般的です。
・妊娠5〜8ヶ月の安定期が最適な理由
妊娠中に歯科検診を受ける最適な時期は妊娠5〜8ヶ月(妊娠中期)とされています。
その理由は、以下のような点が挙げられます。
① つわりが落ち着き、体調が安定する
妊娠初期のつわりが軽減され、多くの妊婦さんが比較的過ごしやすくなる時期です。歯科治療を受ける際に仰向けの姿勢が苦しくなりにくく、ストレスなく治療を受けやすいのが特徴です。
② 胎児の器官形成が完了し、治療による影響が少ない
妊娠初期は胎児の器官が形成される重要な時期ですが、中期になるとこの形成が完了し、安定期に入ります。そのため、歯科治療で使用する麻酔やレントゲン撮影も、適切に管理された環境であれば問題なく受けることができます。
③ 出産前に歯の健康を整えておくことで、産後の負担を減らせる
出産後は赤ちゃんのお世話で忙しくなり、なかなか自分の歯のケアに時間を割くことが難しくなります。そのため、妊娠中にむし歯や歯周病のチェックを受け、必要な処置を済ませておくことが重要です。
・出産前に済ませておきたい歯科治療とその重要性
妊娠中に受けられる治療には制限がありますが、妊娠中期であれば多くの治療を安全に受けることが可能です。
特に、次のような処置を事前に済ませておくと、産後の口腔トラブルを予防できます。
・スケーリング(歯石除去)
妊娠中に歯石がたまりやすくなるため、歯周病の予防としてスケーリングを受けておくと良いでしょう。
・PMTC(プロフェッショナルクリーニング)
セルフケアでは落としきれない汚れを除去し、口腔環境を清潔に保つことができます。
・むし歯の治療
軽度のむし歯であれば、妊娠中期に治療しておくことで、産後の悪化を防げます。
・詰め物や被せ物の調整
妊娠中に歯ぎしりや食いしばりが増えることがあるため、詰め物や被せ物の状態を確認し、必要に応じて調整しておくと良いでしょう。
5. 妊娠中に受けても安全な歯科治療とは?

妊娠中でも可能なむし歯・歯周病治療
-
- 概要: 妊娠中はむし歯や歯周病のリスクが高まるため、軽度のトラブルのうちに適切な治療を受けることが大切です。特に、妊娠中期(5〜8ヶ月)の安定期であれば、多くの歯科治療が安全に受けられます。
-
- むし歯の治療: 軽度のむし歯であれば、通常の治療を受けることが可能です。局所麻酔を使用する場合もありますが、歯科で使用する麻酔は胎児への影響が極めて少ないため、適切に管理された環境であれば問題ありません。
-
- 歯周病の治療(スケーリング・ルートプレーニング): 歯石除去(スケーリング)や歯周ポケットの洗浄(ルートプレーニング)を受けることで、歯周病の進行を防ぎ、母体や赤ちゃんの健康を守ることができます.
-
- PMTC(プロフェッショナルクリーニング): 妊娠中の口腔内はホルモンの影響で細菌が繁殖しやすくなります。PMTCを受けることで、セルフケアでは落としきれない汚れを除去し、むし歯や歯周病のリスクを減らすことができます.
- 注意: 妊娠中でも歯科治療は可能ですが、治療の必要性やリスクを考慮し、事前に歯科医師と相談することが大切です.
妊娠期に避けた方がいい歯科処置とその理由
-
- 抜歯や外科処置: 妊娠中はホルモンバランスの影響で歯ぐきが腫れやすく、外科的な処置を行うと出血や炎症が起こりやすいため、抜歯やインプラント治療などの外科処置は出産後に延期するのが一般的です.
-
- 長時間の治療: 妊娠後期になると、長時間の治療が体に負担をかけるため、30分〜1時間以内の短時間で終わる処置が推奨されます。特に仰向けの姿勢が辛くなる時期は、治療を分けて行うなどの配慮が必要です.
-
- ホワイトニング: 美容目的の処置であり、使用する薬剤の胎児への影響について十分な研究データがないため、妊娠中は避けるのが一般的です.
- 注意: 治療の必要性や緊急度によって判断が分かれるため、歯科医師と相談しながら適切な処置を選択することが重要です.
麻酔やX線検査は赤ちゃんに影響を与えないのか?
-
- 歯科麻酔の安全性: 歯科治療で使用される局所麻酔は、胎盤を通過する量が極めて少なく、赤ちゃんに悪影響を及ぼすリスクはほとんどありません。ただし、妊娠初期や後期では避けた方が良い場合もあるため、使用する際は歯科医師と相談してください.
-
- X線検査(レントゲン)の影響: 歯科で行うX線検査は、放射線量が非常に少なく、さらに鉛のエプロンを着用することで胎児への影響をほぼゼロに抑えられます。ただし、妊娠初期はできるだけX線検査を避けるのが一般的です.
- 薬の服用について: 歯科治療の際に処方される抗生物質や鎮痛剤の中には、妊娠中に避けた方がよいものもあります。自己判断で薬を中断せず、必ず歯科医師の指示に従うようにしましょう.
6. つわりがあるときの歯磨きの工夫と口腔ケアのポイント

歯磨き粉の選び方とつわり中でも快適に磨く方法
-
- 概要: つわりがあると、歯磨きの際に歯ブラシを口に入れるだけで吐き気を感じたり、歯磨き粉の香りや味に敏感になったりすることがあります。そのため、歯磨き粉の選び方や歯磨きの仕方を工夫することで、不快感を軽減できます。
-
- ミントが強すぎない歯磨き粉を選ぶ: 歯磨き粉の刺激が強いと、つわり中は特に気持ち悪く感じることがあります。無香料やフルーツフレーバーの歯磨き粉を試してみると、吐き気を抑えながら磨くことができるかもしれません。
-
- 歯磨き粉なしで磨いてみる: 歯磨き粉の味や香りがつらい場合は、水だけで歯を磨く方法もあります。歯磨き粉なしでも十分に歯垢を落とすことができるため、つわりが落ち着くまで無理せず水磨きに切り替えるのも良いでしょう.
-
- 小さめの歯ブラシやヘッドが薄いものを使う: 歯ブラシのヘッドが大きいと、奥歯を磨く際に吐き気を誘発することがあります。ヘッドがコンパクトなタイプや、薄いデザインの歯ブラシを選ぶと、負担を軽減できます.
-
- 歯磨きの時間を短縮する: 長時間歯を磨くと気持ち悪くなりやすいため、短時間でサッと磨き、回数を増やすことを意識しましょう。1回3分を目安に、朝・昼・晩の3回に分けるのが理想的です.
うがい薬やフッ素ジェルを活用するセルフケア
-
- 概要: つわりが強いときは、どうしても歯磨きが難しくなる日もあります。そのようなときは、無理に磨こうとせず、うがい薬やフッ素ジェルを活用するのがおすすめです.
-
- うがい薬で口内の清潔を保つ: 歯磨きが難しい日は、抗菌作用のあるマウスウォッシュでうがいをするだけでも、口内の細菌の増殖を抑えることができます。ただし、アルコール成分が含まれているものは刺激が強いため、ノンアルコールタイプを選ぶと良いでしょう.
-
- フッ素ジェルで歯を強化する: つわり中は食事の頻度が増えるため、むし歯のリスクも高まります。フッ素入りのジェルを塗布することで、歯の再石灰化を促進し、むし歯予防につながります。ただし、妊娠中に使用できるフッ素濃度の低いタイプを選ぶことが大切です.
- キシリトールガムを活用する: ガムを噛むことで唾液の分泌が促され、口内の汚れを洗い流す効果が期待できます。キシリトール配合のガムを噛むことで、むし歯菌の増殖を抑えることも可能です。ただし、糖分が含まれていないものを選ぶようにしましょう.
食後すぐの歯磨きはNG?吐き気を抑えつつケアする方法

-
- 概要: つわりが強いときは、食後すぐに歯磨きをすると吐き気を感じることがあります。また、胃酸が逆流しやすい妊娠期は、食後すぐの歯磨きが歯にダメージを与える可能性があるため、注意が必要です.
-
- 食後30分ほど時間を空ける: 食事をした直後は、胃酸が口の中に広がっているため、すぐに歯磨きをすると歯のエナメル質が傷つきやすくなります。そのため、食後はまず水やお茶で口をすすぎ、30分ほど経ってから歯磨きをするのが理想的です.
-
- 水やお茶でこまめに口をすすぐ: つわりがひどいときは、こまめに水やお茶でうがいをするだけでも効果的です。これにより、口内の酸を中和し、むし歯のリスクを軽減できます.
- 無理に歯磨きをしない日もOK: つわりの症状が特にひどい日は、無理に歯磨きをしようとするとストレスになってしまいます。その場合は、うがい薬を使用したり、フッ素ジェルを塗るだけでも構いません。大切なのは、できる範囲で口腔ケアを続けることです.
7. 妊娠中の食生活と歯の健康の関係

・妊娠期におすすめの栄養素(カルシウム・ビタミンDなど)
妊娠中は、赤ちゃんの骨や歯の形成に必要な栄養素をしっかり摂取することが大切です。
とくに、歯の健康維持に欠かせない栄養素として、以下のものが挙げられます。
・カルシウム
カルシウムは、赤ちゃんの骨や歯の形成に必要な栄養素です。妊娠中にカルシウムが不足すると、母体の骨や歯のカルシウムが溶け出し、骨粗しょう症や歯のトラブルを引き起こす可能性があります。牛乳やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品、小魚、大豆製品を積極的に摂るようにしましょう。
・ビタミンD
ビタミンDは、カルシウムの吸収を助ける働きがあります。妊娠中にビタミンDが不足すると、カルシウムを十分に利用できず、歯や骨の健康が損なわれることがあります。鮭、いわし、卵黄、きのこ類に多く含まれており、日光を適度に浴びることで体内での合成も促されます。
・マグネシウム
マグネシウムはカルシウムとともに歯や骨を強化する重要なミネラルです。マグネシウムが不足すると、骨や歯がもろくなる可能性があります。ナッツ類、海藻類、玄米、大豆製品などをバランスよく摂取しましょう。
・ビタミンC
ビタミンCは歯ぐきの健康を維持するために必要な栄養素です。妊娠中は歯肉炎になりやすいため、パプリカ、ブロッコリー、キウイ、いちごなどの野菜や果物を積極的に摂ると、歯ぐきの炎症を予防することができます。
・間食が増える時期に気をつけるべき食品と食べ方
妊娠中は、ホルモンバランスの変化や胃の圧迫により、一度にたくさんの食事を摂るのが難しくなり、間食の回数が増えることがよくあります。
しかし、間食が増えると口の中が酸性になりやすくなり、むし歯や歯周病のリスクが高まります。以下のポイントを意識して、歯に優しい間食を選びましょう。
・糖分の多いお菓子やジュースは控える
妊娠中は甘いものが欲しくなることがありますが、糖分が多い食べ物や飲み物はむし歯の原因になりやすいため、頻繁に摂るのは避けた方が良いでしょう。特に、砂糖が多く含まれるチョコレートやクッキー、炭酸飲料などは口の中に長く残りやすいため、摂取量に注意が必要です。
・キシリトールガムやナッツ類を活用する
どうしても間食をしたい場合は、キシリトール入りのガムを噛むことで唾液の分泌を促し、口内環境を整えるのがおすすめです。また、ナッツ類は糖分が少なく、歯に優しい間食として適しています。
・食べる時間を決めて「だらだら食べ」を防ぐ
間食が増えると、口の中が常に酸性の状態になり、むし歯のリスクが高まります。食事の回数を決め、だらだらと食べ続けないようにすることが大切です。間食をするときは、食後にまとめて摂るか、歯磨きやうがいができるタイミングを選びましょう。
・妊娠中に控えたい飲食物(酸性食品・糖分の多い食品)
妊娠期の口腔ケアを考えるうえで、控えた方が良い飲食物にも注意が必要です。
とくに、酸性食品や糖分の多い食品は、歯のエナメル質を傷つけたり、むし歯のリスクを高めたりする可能性があるため、過剰に摂取しないように気をつけましょう。
・柑橘類や酢を多く含む食品
レモンやオレンジなどの柑橘類、酢の効いたドレッシングや梅干しなどは、エナメル質を溶かしやすいため、食べた後は水で口をすすぐようにしましょう。
・炭酸飲料やスポーツドリンク
炭酸飲料やスポーツドリンクは、糖分と酸が多く含まれており、歯にとって非常にダメージが大きいため、摂取を控えるのが理想的です。どうしても飲みたい場合は、ストローを使って直接歯に当たらないようにすると良いでしょう。
・キャラメルやグミなどの粘着性の高いお菓子
キャラメルやグミ、ソフトキャンディーなどは、歯にくっつきやすく、むし歯の原因になりやすいため、できるだけ避けることをおすすめします。
8. 妊婦さんの歯科検診はどこで受けられる?

自治体の妊婦歯科検診の活用方法
-
- 概要: 多くの自治体では、妊娠期の健康管理の一環として「妊婦歯科検診」を実施しています。これは、妊婦さんが無料または低価格で歯科検診を受けられる制度で、妊娠中の口腔トラブルを早期発見し、必要に応じた治療を受けることができる仕組みです。
-
- 自治体の母子健康手帳に情報が記載されている: 自治体の妊婦歯科検診は、母子健康手帳に記載されていることが多いため、まずは手帳を確認しましょう。さらに、自治体のウェブサイトや役所の保健センターで詳細が案内されている場合もあります。
-
- 無料または低料金で受けられる: 自治体の制度によって異なりますが、多くの場合、妊婦歯科検診は無料または1,000円程度の低料金で受けられます。費用負担が少ないため、積極的に活用しましょう。
- 対象期間と受診可能な歯科医院を確認する: 自治体の妊婦歯科検診は、妊娠中の一定期間のみ受診可能な場合が多いです。妊娠が分かったら早めに確認し、指定の歯科医院でのみ受診できるケースは事前に予約を取ることをおすすめします。
産婦人科と歯科医院の連携が重要な理由
-
- 概要: 妊娠中の歯科検診や治療を受ける際は、産婦人科と歯科医院が連携しているかどうかを確認することが重要です。妊娠中は体調の変化が大きいため、歯科治療にも細心の注意が必要です。
-
- 産婦人科での相談を忘れずに: 歯科検診や治療を受ける前に、かかりつけの産婦人科で相談することをおすすめします。特に持病がある場合や妊娠経過に不安がある場合は、事前に産婦人科の医師と相談し、安全に受診できるよう準備しましょう。
-
- 歯科治療時に配慮すべきポイントを確認する: 妊娠中の歯科治療では、麻酔やX線検査の使用可否、治療姿勢などに配慮が必要です。妊娠中の方を多く診療している歯科医院を選ぶと安心です。
- 妊娠期に応じた治療計画を立てられる: 産婦人科と連携している歯科医院では、妊娠初期・中期・後期に応じた無理のない治療計画を立ててくれるため、妊婦さんも安心して受診できます。
妊娠中に歯科医院を選ぶ際のポイント
-
- 妊婦の受診に慣れている歯科医院を選ぶ: 妊娠中の口腔ケアには特別な配慮が必要です。診療経験が豊富な歯科医院を選ぶことで、安全に治療を受け、妊娠期の口腔トラブルに適したアドバイスをもらえます。
-
- 妊婦さん専用の診療枠があるか確認する: 妊娠中は体調が変わりやすいため、診療時間や治療の進め方を柔軟に対応してくれる歯科医院を選ぶと安心です。妊婦専用の診療枠を設けているクリニックでは、短時間で負担の少ない治療が可能です。
- 治療前に妊娠中であることを必ず伝える: 歯科検診や治療を受ける際は、必ず事前に妊娠していることを伝えましょう。体調が不安定になりやすい時期なので、妊娠の週数や経過を共有し、無理のない範囲で診療を進めてもらうことが大切です。
9. 出産後の口腔ケアの重要性

出産後に歯ぐきが悪化しやすい理由とは?
-
- 概要: 妊娠中はホルモンバランスの影響で歯ぐきの炎症が起こりやすく、出産後もしばらくの間その影響が続くことがあります。また、出産後は育児によるストレスや生活リズムの変化により、口腔ケアが疎かになりがちです。
-
- ホルモンバランスの変化が続く: 妊娠中に増加していた女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)が出産後に急激に減少し、それに伴い歯ぐきの免疫機能も低下しやすくなります。その結果、歯周病菌が活性化し、歯ぐきの炎症が長引くことがあります。
-
- 育児による睡眠不足とストレス: 出産後は赤ちゃんの夜泣きや授乳などで睡眠不足になり、ストレスが増加します。これにより体の免疫機能が低下し、歯ぐきの炎症が治りにくくなり、歯周病が進行するリスクが高まります。
- 食事の乱れと間食の増加: 授乳によるエネルギー消費の増加で間食の回数が増える一方、歯磨きの時間が取れずむし歯のリスクが高まります。特に、甘いものの頻繁な摂取は口腔内の酸性環境を長く続かせ、歯のエナメル質が溶けやすくなります。
授乳期・育児中に気をつけたい歯と歯ぐきのケア
-
- 概要: 出産後は育児に追われ、自分のケアが後回しになりがちですが、可能な限り口腔ケアを継続することが重要です。忙しい中でも実践できる方法を取り入れましょう。
-
- 忙しくても1日2回はしっかり歯磨きを: 毎食後の歯磨きが難しい場合でも、朝と寝る前の2回は必ず歯を磨くことで、むし歯や歯周病のリスクを抑えられます。特に、就寝前は唾液分泌量が減少するため重要です。
-
- 洗口液やフロスを活用する: 時間が取れない場合は、殺菌成分入りの洗口液やフロス、歯間ブラシを使って、歯と歯の間の汚れを効率よく除去しましょう。
- 水分補給をこまめに行い、口腔内の乾燥を防ぐ: 授乳中は体内の水分が失われやすく、口腔内が乾燥しがちです。こまめな水分補給により、むし歯や歯周病のリスクを軽減しましょう。
赤ちゃんの口腔ケアはいつから始めるべき?
-
- 概要:
赤ちゃんの歯の健康を守るためには、母親の口腔ケアに加え、赤ちゃん自身のケアも早めに始めることが大切です。これにより、将来的なむし歯のリスクを低減できます。
- 概要:
-
- 授乳後の口の中を清潔にする: 赤ちゃんの歯が生える前でも、授乳後にガーゼや綿棒で口の中を優しく拭き、細菌の増殖を防ぎます。特に夜間は口腔内が乾燥しやすいため、清潔さを保つことが重要です。
-
- 歯が生え始めたらシリコン製の歯ブラシを活用: 生後6ヶ月頃から、シリコン製のやわらかい歯ブラシを使い、軽くブラッシングする習慣をつけることで、自然な口腔ケアの習慣を促します。
- 母親がむし歯菌を赤ちゃんに移さない工夫を: むし歯菌は親から子へ移ることが多いため、母親自身の口腔ケアを徹底し、口移しで食べ物を与えたり、赤ちゃん用スプーンの共有を避けるなどの工夫が必要です。
10. 妊娠中の歯科検診を習慣化し、母子ともに健康な口腔環境を守るために

・妊娠期の歯科検診を受けるメリットのまとめ
-
- 妊娠期の歯科検診のメリット
妊娠期の歯科検診は、むし歯や歯周病のチェックだけでなく、妊娠中ならではの口腔環境の変化を把握し、適切なケアを行うために必要です。
- 妊娠期の歯科検診のメリット
-
- 口腔トラブルの早期発見
ホルモンバランスの変化により、歯周病やむし歯のリスクが高まるため、症状が出る前に検診を受けることで、軽度のうちに対処でき、快適な妊娠生活を送ることができます。
- 口腔トラブルの早期発見
-
- 計画的な治療の実施
妊娠中に口腔内の状態を把握しておくことで、出産後に必要な治療を計画的に進めることが可能になり、育児による負担を軽減できます。 - 赤ちゃんの健康への影響
妊娠中に歯周病が進行すると、早産や低体重児出産のリスクが高まるため、検診を通じて予防することが赤ちゃんの健康を守ります。
- 計画的な治療の実施
・妊娠中の歯科ケアが赤ちゃんの健康につながる理由
-
- 母親の口腔内環境の影響
妊娠中に歯周病が悪化すると、歯周病菌が血液を通じて胎盤に影響を及ぼし、早産や低体重児のリスクが高まるため、早期発見が重要です。
- 母親の口腔内環境の影響
-
- 赤ちゃんの口腔環境は母親の影響を受けやすい
母親の口腔内環境が良くない場合、唾液を介してむし歯菌が赤ちゃんに移る可能性があるため、清潔な状態を維持することが大切です。 - 生活習慣の影響
妊娠期の食生活や生活習慣は、赤ちゃんの歯の発育に影響します。カルシウムやビタミンDなどの適切な栄養摂取が求められます。
- 赤ちゃんの口腔環境は母親の影響を受けやすい
・歯科医院での相談と継続的なケア
-
- まずは歯科医院で相談
妊娠中の歯科検診は、母親と赤ちゃんの健康を守る大切なステップです。まずは歯科医院に相談し、不安を解消しましょう。
- まずは歯科医院で相談
-
- 適切なアドバイスの取得
口腔内の状態をチェックしてもらい、妊娠期に適したケア方法についてアドバイスを受けることができます。
- 適切なアドバイスの取得
-
- 安心して受けられる検診の活用
自治体によっては、妊婦向けの無料歯科検診を実施している場合があり、これを活用することで安心して出産に臨むことができます。 - 継続的な歯科ケアの習慣化
妊娠期に検診を習慣化することで、出産後も定期的な検診を受け、親子で健康な口腔環境を維持することが可能になります。
- 安心して受けられる検診の活用
お気軽にご相談ください!予約・お問い合わせの方法
◎予約方法
・電話予約:診療時間内にお電話いただければ、スタッフが丁寧に対応いたします。
・オンライン予約:当院のウェブサイトから24時間いつでもご予約いただけます。ご希望の日時や治療内容を選択し、簡単に予約手続きが完了します。
◎お問い合わせ対応
診療内容やお子さんの症状についてのご質問も、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なスタッフが、保護者の方の疑問や不安に寄り添いながらお答えします。
監修:愛育クリニック麻布歯科ユニット
所在地〒:東京都港区南麻布5丁目6-8 総合母子保健センター愛育クリニック
電話番号☎:03-3473-8243
*監修者
愛育クリニック麻布歯科ユニット
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会
カテゴリー:コラム 投稿日:2025年2月27日

