子どもが指しゃぶりをやめない?歯並びや発育への影響とは
はじめに:なぜ指しゃぶりが気になるのか?

・指しゃぶりは自然な行動?それともやめさせるべき?
赤ちゃんや幼児が指をしゃぶる姿は、多くの親が一度は目にする光景でしょう。
指しゃぶりは生後すぐから始まり、多くの子どもにとっては安心感を得るための行動です。
特に赤ちゃんは、母乳や哺乳瓶を吸う動作を繰り返すことで、吸啜(きゅうてつ)反射が発達し、指を吸うことで落ち着きを感じます。
では、この行動は自然なものなのでしょうか?それとも、できるだけ早くやめさせるべきなのでしょうか?
答えは「年齢による」と言えます。新生児や乳児期に見られる指しゃぶりは正常な成長過程の一部ですが、幼児期を過ぎても続く場合、歯並びや噛み合わせ、口腔機能の発達に影響を及ぼすことがあるため、適切なタイミングでやめることが推奨されます。
ただし、指しゃぶりを無理にやめさせようとすると、逆にストレスを感じてしまい、より頻繁に行うようになることもあります。
そのため、親は焦らずに、子どもの成長と心理的な要因を考慮しながら、適切な対応をしていくことが重要です。
・幼児期の指しゃぶりは発達の一部
指しゃぶりは、幼児の情緒的な安定にも関係しています。
特に1~3歳頃の子どもは、不安を感じたときや眠る前、退屈なときに指しゃぶりをすることで安心感を得ることがよくあります。
これは、赤ちゃんが母親の胸に抱かれて安心するのと同じような感覚です。
また、この時期の指しゃぶりは、口の感覚を発達させる役割も果たしています。
子どもは手や指を口に入れることで、物の感触を学び、五感の発達を促しているのです。
そのため、1~2歳頃までは、指しゃぶりを無理にやめさせる必要はありません。
しかし、3歳を過ぎても頻繁に指しゃぶりをしている場合は、口の周りの筋肉の発達や歯並びに影響を与える可能性があるため、徐々にやめる方向へと導く必要があります。
また、保育園や幼稚園に通い始めると、他の子どもが指しゃぶりをしなくなることで自然にやめるケースも多いですが、そうならない場合は親のサポートが必要になるでしょう。
・いつまでにやめるのが理想?
一般的に、3歳頃までの指しゃぶりは大きな問題にはなりませんが、4~5歳を過ぎても続く場合は、歯並びや噛み合わせに影響を及ぼす可能性があります。
特に、5歳以降になると顎の成長に関わり、永久歯が生えそろう頃には噛み合わせの異常を引き起こすリスクが高まるため、注意が必要です。
指しゃぶりが長期間続くと、以下のような問題が生じることがあります。
- 出っ歯(上顎前突): 指をしゃぶることで上の前歯が前に押し出され、出っ歯になる可能性がある。
- 開咬(かいこう): 前歯が上下で噛み合わず、隙間ができる状態になり、食べ物を噛み切るのが難しくなる。
- 口呼吸の習慣: 指しゃぶりの影響で口を閉じる習慣がなくなり、口呼吸が定着してしまう。
これにより、虫歯や歯肉炎、喉の乾燥による風邪のリスクが高まる。
このような理由から、4~5歳までに指しゃぶりを減らし、6歳頃までには完全にやめることが理想的です。
しかし、子どもによって発達のスピードは異なるため、一概に「何歳までにやめなければならない」という決まりはありません。
大切なのは、子どもの成長を見守りながら、徐々に指しゃぶりの頻度を減らしていくことです。
指しゃぶりが子どもの口元に与える影響

・歯並びや噛み合わせの問題が生じる可能性
子どもが長期間指しゃぶりを続けると、歯並びや噛み合わせに影響を及ぼすことがあります。
特に、3歳を過ぎても頻繁に指しゃぶりをしている場合、指が前歯を前方へ押し出す力となり、歯並びの乱れを引き起こす原因になるのです。
指しゃぶりが歯並びに影響する主な理由は、「持続的な外部からの圧力」です。
指を口の中に入れて吸うことで、上の前歯が前方に傾き、下の前歯は内側に押し込まれることがあります。
これが長期間続くと、上顎と下顎の噛み合わせのバランスが崩れ、以下のような歯列不正が起こりやすくなります。
- 上顎前突(じょうがくぜんとつ): いわゆる「出っ歯」と呼ばれる状態で、前歯が前に押し出されることによって発生します。
- 開咬(かいこう): 上下の前歯が噛み合わず、隙間が空いたままの状態になる。食べ物を噛み切ることが難しくなることもある。
- 交叉咬合(こうさこうごう): 本来なら上の歯が外側に位置するはずの噛み合わせが、指しゃぶりの影響で逆になってしまうことがある。
また、指しゃぶりによる歯並びへの影響は、指をしゃぶる「力の強さ」や「頻度」によっても異なります。
軽くしゃぶる程度なら問題にならないこともありますが、頻繁に強く吸う癖がついている場合は、歯並びに大きな影響を与えるリスクが高くなります。
そのため、子どもが頻繁に指しゃぶりをしている場合は、早めにやめる方向へ導くことが大切です。
・口元の筋肉の発達への影響
指しゃぶりは、単に歯並びの問題を引き起こすだけではなく、口元の筋肉の発達にも影響を与えます。
人間の口周りにはさまざまな筋肉があり、これらの筋肉が正しく発達することで、食事をしたり、正しく発音したりすることができます。
しかし、指しゃぶりが長期間続くと、口周りの筋肉のバランスが崩れ、機能的な問題が生じることがあります。
指しゃぶりが口の筋肉に与える影響
- 口を閉じる力が弱くなる: 指をしゃぶることで口が常に開いた状態になると、口を閉じる筋肉(口輪筋)が発達しにくくなります。その結果、口がぽかんと開いた状態が習慣化しやすくなります。
- 舌の位置が低くなる: 指しゃぶりをしていると、舌が常に下の位置にあるため、正しい舌の使い方を覚えにくくなります。本来、舌は上顎に軽く触れる位置にあるのが理想ですが、指しゃぶりを続けるとこのバランスが崩れ、発音や飲み込みの際に影響が出ることがあります。
- ほうれい線や顔のたるみの原因に: これは成長してからの話ですが、子どもの頃に指しゃぶりの習慣があると、口の周りの筋肉がしっかりと鍛えられず、大人になった際に口元のたるみが目立つこともあります。
特に「口呼吸」の習慣がついてしまうと、口の中が乾燥しやすくなり、虫歯や歯肉炎のリスクが高まるため、早い段階で指しゃぶりを減らしていくことが重要です。
・発音や舌の使い方に関するリスク
指しゃぶりの影響は歯並びや筋肉の発達だけでなく、発音の発達にも関係しています。
幼児期は言葉を覚え、発音を学ぶ大切な時期ですが、指しゃぶりによって舌の位置や口の動きに影響が出ると、正しい発音ができなくなることがあります。
特に影響を受けやすいのが、「サ行」と「タ行」の発音です。
これらの音は舌を上の歯の裏に軽くつけて発音する必要がありますが、指しゃぶりの習慣があると、舌が正しい位置に動きにくくなるため、
「サ行がシャ行になる」「タ行がダ行になる」といった発音の乱れが生じることがあります。
また、指しゃぶりをすることで「舌突出癖(ぜつとっしゅつへき)」という癖がついてしまうこともあります。
これは、発音の際に舌が前歯の間から出てしまう癖のことで、これが続くと正しい発音ができなくなるだけでなく、開咬(かいこう)の原因にもなります。
発音の問題は、幼少期には気にならなくても、就学後や大人になってから気になるケースが多いです。
そのため、幼児期のうちに指しゃぶりをやめ、舌や口の正しい動きを身につけることが大切です。
長期間の指しゃぶりによる歯科的リスクとは?
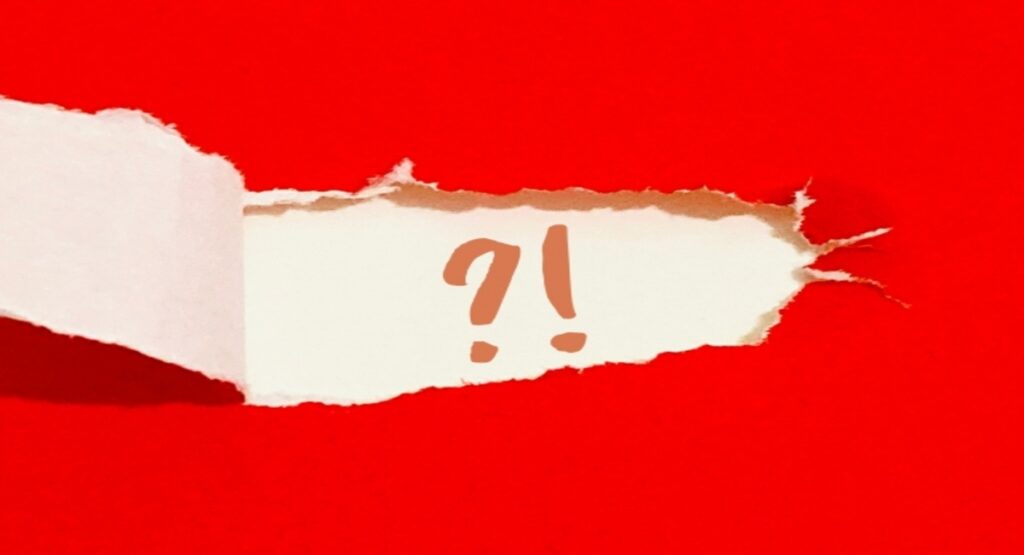
・出っ歯(上顎前突)になりやすい理由
指しゃぶりが長期間続くと、最も影響を受けやすいのが前歯の位置です。
特に、上の前歯が前方に押し出されることで「上顎前突(じょうがくぜんとつ)」、いわゆる出っ歯の状態になることが多くなります。
指しゃぶりの動作では、指を口に入れて強く吸うことで、上の歯に前方向の力がかかります。
これが習慣化すると、前歯が本来の位置よりも前に押し出され、前突した状態になってしまうのです。
また、指を吸う際に下の顎が後退する傾向があるため、上の歯と下の歯の位置関係が崩れ、より出っ歯が目立つようになります。
さらに、出っ歯になることで起こる問題
- 前歯で物を噛み切りにくくなる: 前歯が適切な位置にないと、食べ物をうまく噛み切ることができず、食事に影響が出ることがある。
- 口が閉じにくくなる: 出っ歯になると、口を自然に閉じることが難しくなり、常に口が開いた状態になりやすい。
- 外傷リスクが高まる: 前歯が前に突出していると、転倒した際に歯が欠けたり折れたりするリスクが高まる。
このように、指しゃぶりによる上顎前突は、単なる見た目の問題だけでなく、口腔機能や日常生活にも影響を及ぼすため、早めの対応が必要です。
・開咬(前歯が噛み合わない状態)への影響
指しゃぶりによるもう一つの大きな歯列不正が、「開咬(かいこう)」です。
開咬とは、上下の前歯がしっかりと噛み合わず、隙間ができてしまう状態を指します。
開咬が起こる主な原因は、指をしゃぶる際に前歯にかかる圧力と、舌の位置の影響です。
指をしゃぶる動作では、指が前歯の間に入り込むため、前歯が外側に押し出されると同時に、上下の歯が適切に噛み合わなくなります。
また、指しゃぶりをしている子どもは、舌を前に突き出す癖がつきやすく、これがさらなる開咬の悪化を招くこともあります。
開咬が続くことで起こる問題
- 食事の際に食べ物を噛み切るのが難しくなる: 特に麺類や肉類など、前歯で噛み切る必要のある食べ物を食べる際に影響が出やすい。
- 発音に影響を与える: 「サ行」や「タ行」の発音が不明瞭になり、話し方に違和感が出ることがある。
- 顎関節症のリスクが高まる: 噛み合わせのバランスが崩れることで、顎関節に負担がかかりやすくなる。
開咬は自然に改善するケースもありますが、指しゃぶりを長期間続けた場合、成長とともに噛み合わせのズレが固定化し、矯正治療が必要になることもあります。
そのため、4~5歳頃には指しゃぶりをやめる方向へ進めることが望ましいでしょう。
・口呼吸の習慣がつく可能性
指しゃぶりが長く続くと、歯並びの乱れだけでなく、「口呼吸の習慣」が定着してしまうこともあります。
本来、人間は鼻呼吸が理想的ですが、指しゃぶりをしていると口が開いた状態が続くため、口で呼吸をする癖がついてしまうのです。
口呼吸のデメリット
- 虫歯や歯肉炎のリスクが高まる: 口を開けたままでいると、口の中が乾燥しやすくなり、唾液の分泌が減少します。
唾液には虫歯を防ぐ効果があるため、口が乾くことで虫歯や歯肉炎になりやすくなるのです。 - 風邪をひきやすくなる: 鼻呼吸では、鼻の粘膜が空気中のホコリや細菌を取り除くフィルターの役割を果たします。
しかし、口呼吸をしていると、直接喉に空気が入るため、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。 - 顔つきや発音に影響を与える: 口呼吸の習慣がつくと、口周りの筋肉が適切に発達せず、顔全体のバランスが崩れることがあります。
具体的には、「口元が前に出る」「顎が小さくなる」「顔が縦に長くなる」などの影響が出る可能性があります。
さらに、口が常に開いた状態で話すと、発音が不明瞭になりやすく、特に「マ行」「バ行」「パ行」の発音が弱くなることがあります。
指しゃぶりが習慣化すると、歯並びや噛み合わせだけでなく、呼吸や発音にも影響を及ぼす可能性があります。
そのため、できるだけ早い段階で指しゃぶりを減らし、正しい口腔機能を育てていくことが大切です。
指しゃぶりが続くと顔立ちにも影響する?

・顎の成長バランスの崩れ
指しゃぶりが長期間続くと、歯並びや噛み合わせだけでなく、顎の成長そのものに影響を与える可能性があります。
特に、3歳以降も頻繁に指しゃぶりをしている場合、上顎と下顎の発達バランスが崩れ、顔全体の成長に影響を及ぼすことがあります。
人間の顎は、成長とともに少しずつ前後・左右に発達していきます。
しかし、指しゃぶりが続くと、口の中で指が持続的な圧力をかけるため、上顎が過度に前方へ成長したり、逆に下顎の成長が抑えられたりすることがあります。
その結果、以下のような問題が発生することがあります。
- 上顎が発達しすぎる(上顎前突): 指しゃぶりの圧力によって、上顎が前方へ押し出され、上の前歯が突出した状態になることがあります。この影響で口元が前に出た印象になり、見た目のバランスが崩れる可能性があります。
- 下顎の成長が抑えられる(下顎後退): 指しゃぶりの習慣があると、下顎が正常な位置に成長するのを妨げることがあります。特に、指を吸う動作によって下顎が後ろに押し込まれるため、下顎の発達が遅れ、顔全体が「引っ込んだ」ような印象になることもあります。
- 顎の左右のバランスが崩れる(非対称成長): 指しゃぶりをするときに、左右どちらか一方の指を吸う癖があると、片側の顎にのみ負荷がかかることがあります。その結果、顎が非対称に成長し、顔のバランスが左右で崩れることもあるのです。
顎の成長バランスが崩れると、見た目だけでなく、噛み合わせや咀嚼機能にも影響を及ぼします。
噛み合わせが悪くなると、歯並びの問題が進行しやすくなり、将来的に矯正治療が必要になることがあるため、指しゃぶりはできるだけ早めに卒業するのが理想的です。
・口元の形やフェイスラインへの影響
指しゃぶりが続くと、顔の成長に影響が出るだけでなく、口元の形やフェイスラインにも変化が生じることがあります。
特に、長期間の指しゃぶりは、口周りの筋肉の発達や骨格の形成に影響を与えるため、以下のような特徴が現れやすくなります。
- 口が常に開いた状態になりやすい(口呼吸習慣): 指しゃぶりの影響で口の周りの筋肉が十分に発達しないと、口を閉じる力が弱くなります。その結果、口呼吸の癖がつきやすくなり、口元がぽかんと開いた状態になりやすくなるのです。これは見た目の印象にも影響し、「だらしない印象」を与えることもあります。
- ほうれい線が深くなる可能性がある: 口元の筋肉が適切に発達しないと、頬のたるみが進行しやすくなります。その結果、成長してから「ほうれい線が深くなる」「頬が下がる」などの影響が出ることがあります。特に、幼少期に指しゃぶりが長期間続いていた場合、成人後の顔立ちに影響を及ぼす可能性があります。
- 顎が細長くなりやすい(面長傾向): 指しゃぶりの習慣があると、上下の歯の噛み合わせが悪くなり、口周りの筋肉が正常に働かない状態になります。その影響で、顎が縦に長く成長し、顔全体が細長い印象になりやすくなるのです。これは、特に開咬の影響を受けやすいケースでよく見られます。
顔立ちに関する影響は、成長とともに目立ってくることが多く、幼児期には気にならなくても、小学校高学年や思春期になってから気になることが増えます。
そのため、できるだけ幼少期のうちに指しゃぶりを減らし、自然な顔の成長を促すことが大切です。
・大人になっても残る可能性のある癖
指しゃぶりが長く続いた子どもの場合、幼少期にやめられたとしても、その影響が大人になってからも残ることがあります。
例えば、以下のような癖が残ることが考えられます。
- 舌を前に押し出す癖(舌突出癖): 指しゃぶりをしていると、舌を前歯の間から押し出す癖がつくことがあります。この癖が残ると、食事の際に正しく噛めなかったり、発音が不明瞭になったりすることがあります。
- 無意識に口を開ける癖: 指しゃぶりの影響で口周りの筋肉が適切に発達していないと、無意識のうちに口が開いてしまうことがあります。これは、歯並びや見た目の問題だけでなく、口呼吸による健康リスク(虫歯・歯肉炎・喉の乾燥など)にもつながります。
- 頬杖や片側噛みの癖が残る: 指しゃぶりの影響で顎の左右バランスが崩れた場合、大人になってからも頬杖をついたり、片側の歯ばかりで噛む癖が残ることがあります。これにより、さらに顔の歪みが進行する可能性があります。
こうした癖は、指しゃぶりをやめても無意識に残ってしまうことがあるため、指しゃぶりをやめるだけでなく、その後の口腔習慣も整えることが重要です。
特に、歯並びや噛み合わせに問題がある場合は、早めに歯科医院で診てもらい、必要に応じて矯正治療を受けることも検討しましょう。
やめさせるべきタイミングと対策
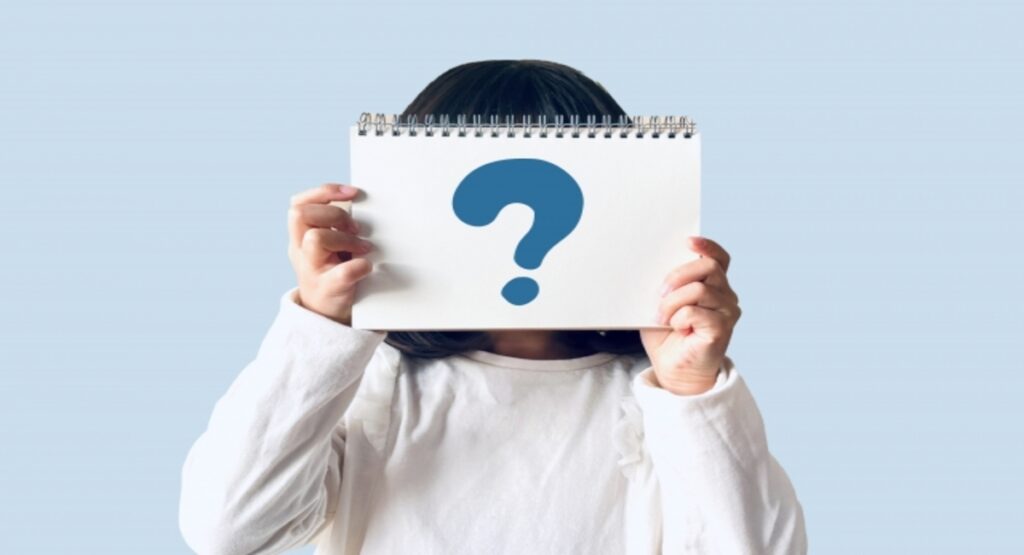
・自然にやめる子もいる?
指しゃぶりは多くの子どもに見られる行動ですが、すべての子が親の介入なしに自然とやめるわけではありません。
一般的には、成長とともに周囲の環境の変化や興味の移り変わりにより、指しゃぶりをやめるケースが多いです。
特に、保育園や幼稚園に通い始めると、他の子どもたちが指しゃぶりをしていないことに気づき、自然とやめることがあります。
また、年齢が上がるにつれて、手を使う遊びやおもちゃへの関心が高まり、指しゃぶりをする時間が減少することも多いです。
しかし、中には4~5歳を過ぎても指しゃぶりの習慣が続く子どももおり、何らかの対策が必要になる場合があります。
自然にやめる子の特徴
- 指しゃぶりが特定のシチュエーション(寝る前、退屈なときなど)のみに限定されている
- 周囲の変化(保育園・幼稚園入園、友達との遊びの増加)によって行動が変わる
- 本人が無意識に指しゃぶりを減らしていく傾向がある
やめさせるサポートが必要なケース
- 4~5歳になっても頻繁に指しゃぶりをしている
- 歯並びに影響が出始めている(前歯が前に出ている、開咬が見られるなど)
- ストレスや不安を感じると指しゃぶりがひどくなる
このような場合、親が上手にサポートしながら、指しゃぶりをやめる方向へ導いていくことが重要になります。
・3歳・5歳・7歳がポイントになる理由
指しゃぶりをやめるタイミングとして、特に3歳、5歳、7歳の時期が重要とされています。
これは、それぞれの年齢で口腔や心理の発達に大きな変化があるためです。
3歳:自我の発達と生活習慣の確立
3歳頃になると、自我が発達し、周囲の影響を受けやすくなります。
また、幼稚園や保育園に通い始めることで、指しゃぶりをする環境が変化し、自然とやめるきっかけを得ることがあります。
この時期は、「指しゃぶりをしないとかっこいいね」「お兄さん・お姉さんになったね」といったポジティブな声かけが効果的です。
また、手遊びや工作など、指を使う遊びを積極的に取り入れることで、指しゃぶりをする時間を減らしていくことができます。
5歳:歯並びや噛み合わせに影響が出始める
5歳頃になると、乳歯の歯並びが完成し、永久歯への生え替わりが始まる準備段階に入ります。
この時期までに指しゃぶりをやめないと、出っ歯や開咬などの噛み合わせの異常が固定化しやすくなるため、特に注意が必要です。
また、言語の発達も進む時期なので、指しゃぶりによる舌の癖が発音に影響を与えることもあります。
「サ行がうまく言えない」「舌を前に出して話す癖がある」などの兆候が見られたら、指しゃぶりをやめるサポートを本格的に始めるタイミングです。
7歳:永久歯の生え替わりが始まる
7歳になると、前歯の永久歯が生え揃い始めます。
この時期までに指しゃぶりをやめないと、歯並びの異常が永久歯にも影響し、矯正治療が必要になるケースが増えます。
このため、6歳までには完全に指しゃぶりを卒業することが理想的です。
もし7歳になっても指しゃぶりが続いている場合は、歯科医院で相談し、専門的なアプローチを検討することをおすすめします。
・焦らず進めるための親のサポート
指しゃぶりをやめさせる際、最も重要なのは「無理にやめさせないこと」です。
特に、強制的に指しゃぶりを禁止すると、子どもがストレスを感じ、逆に指しゃぶりの頻度が増えてしまうことがあります。
そのため、焦らず、子どもの気持ちに寄り添いながら進めることが大切です。
親ができるサポート方法
1. 指しゃぶりの理由を理解する
子どもが指しゃぶりをする理由はさまざまです。
退屈だから、眠いから、不安だから、安心感を得たいからなど、指しゃぶりが子どもにとってどんな役割を果たしているのかを考えることが重要です。
例えば、「夜寝る前だけ指しゃぶりをする」という場合は、寝る前のリラックス習慣として指しゃぶりが定着している可能性があります。
その場合、ぬいぐるみを抱く、オルゴールを聞く、親が手を握ってあげるなど、指しゃぶりの代わりになる方法を提案すると効果的です。
2. 小さな成功を褒める
いきなり「今日から指しゃぶり禁止!」とするのではなく、少しずつやめられるように導くことが大切です。
例えば、「お昼の間は指しゃぶりしないで過ごせたね」「今日は寝るときに少しだけだったね」といった小さな成功を褒めることで、子ども自身が「やめることができる」という自信を持てるようになります。
3. 指しゃぶりをしにくい環境を作る
指しゃぶりは無意識に行っていることが多いため、手を使う遊びを増やしたり、爪に苦い味の塗料を塗ったりすることで、物理的に指しゃぶりをしにくくするのも一つの方法です。
ただし、無理に制限しすぎるとストレスになるため、子どもの性格や様子を見ながら進めることが大切です。
子どもが無理なく指しゃぶりを卒業できる方法

・指しゃぶりをしてしまう心理的な原因を考える
指しゃぶりは単なる癖ではなく、子どもにとって心理的な安心材料になっていることが多いです。
そのため、やめさせようとする前に、なぜ指しゃぶりをするのか、その原因を理解することが重要です。
子どもが指しゃぶりをする理由
- 安心感を得るため: 赤ちゃんが母乳や哺乳瓶を吸う動作に似ているため、指しゃぶりをすることで安心感を得ようとします。特に、眠る前や疲れたときに指しゃぶりをする子が多いのはこのためです。
- 退屈だから: 手持ち無沙汰なときに指しゃぶりをすることもあります。例えば、テレビを見ているときや何もすることがないときに、無意識に指を口に入れてしまうことがあります。
- ストレスや不安の表れ: 環境の変化(幼稚園や保育園への入園、引っ越し、家族の変化など)による不安や緊張が、指しゃぶりとして表れることがあります。この場合、無理にやめさせると逆にストレスが増え、指しゃぶりが悪化する可能性があります。
- 癖として定着している: 小さい頃からの習慣が残り、特に理由がなくても指しゃぶりを続けているケースもあります。これが長く続くと、無意識のうちに指しゃぶりをしてしまい、やめたくてもやめられない状態になることがあります。
指しゃぶりをやめるためには、子どもの気持ちに寄り添い、安心できる環境を作ることが大切です。
ただ単に「やめなさい!」と叱るのではなく、代替行動を提案したり、子どもがストレスを感じにくい環境を整えたりすることが効果的です。
・代替行動(ぬいぐるみやタオル)を活用する
指しゃぶりをやめさせるためには、指を吸う代わりになる安心材料を見つけることが有効です。
特に、眠る前や不安を感じたときに指しゃぶりをしている場合、別の方法で安心感を得られるようにすることで、自然に指しゃぶりの頻度を減らすことができます。
指しゃぶりの代わりになる行動
- ぬいぐるみやタオルを持たせる: 指しゃぶりの代わりに、お気に入りのぬいぐるみやタオルを持たせることで、安心感を得られるようにします。特に、子どもが気に入ったものを選ぶことで、より効果が期待できます。
- ハンドトイ(手遊び用のおもちゃ)を活用する: 指を口に入れる代わりに、手で触れることができるおもちゃを持たせるのも良い方法です。例えば、小さなぬいぐるみや手を動かして遊べるおもちゃを持たせると、指しゃぶりをする時間が減ることがあります。
- 手をつなぐ: 親がそばにいるときは、子どもの手を優しく握ってあげるのも効果的です。特に寝る前に指しゃぶりをする場合、「ママが手をつないであげるね」と言って、安心感を与えることで指しゃぶりを防ぐことができます。
- 手を使う遊びを増やす: 手を使う遊び(お絵かき、粘土遊び、ブロック遊びなど)を積極的に取り入れることで、指しゃぶりをする時間を減らしていくことができます。また、指先を動かすことで脳の発達にも良い影響を与えます。
指しゃぶりの代わりになる行動を見つけることで、子どもが無理なくやめられるようになります。
ただし、最初は新しい習慣に慣れるまで時間がかかることもあるため、焦らず少しずつ進めていくことが大切です。
・ご褒美作戦やポジティブな声かけの大切さ
指しゃぶりをやめるためには、子ども自身が「やめたい」と思えるように促すことが重要です。
そのためには、ご褒美作戦やポジティブな声かけを活用することで、指しゃぶりをやめるモチベーションを高めることができます。
ご褒美作戦
- 「指しゃぶりをしなかったらシールを貼る」など、具体的な目標を設定し、達成したときにご褒美をあげる方法は、多くの子どもに効果的です。
- 指しゃぶりをしなかった日にはカレンダーにシールを貼る
- 1週間続けられたら、好きな絵本やおもちゃをプレゼントする
- 「今日は指しゃぶりしなかったね!」と褒めることで、成功体験を積み重ねる
ただし、大きなご褒美を設定しすぎると、「ご褒美がないとやめられない」という状態になってしまうため、
あくまでモチベーションを高める手段として活用するのが理想的です。
ポジティブな声かけ
指しゃぶりをやめる過程で、子どもが「やめたくない」「無理かも」と思うこともあります。
そのときに「どうしてまたやってるの!」「もうお兄ちゃん(お姉ちゃん)なのにやめなさい!」と怒るのは逆効果です。
代わりに、次のようなポジティブな声かけを意識しましょう。
- 「昨日より少し減ったね!すごいね!」(少しずつやめられるようになっていることを認める)
- 「○○ちゃんは頑張ってるね!」(努力をしていることを褒める)
- 「指しゃぶりしないと、お口がきれいになるよ!」(やめることで得られるメリットを伝える)
子どもは「自分が頑張っていることを認めてもらいたい」と感じるものです。
そのため、成功したときは積極的に褒めることで、やめる意欲が高まります。
歯科医院でできる指しゃぶり対策とは?

・歯科医師ができるサポート
指しゃぶりが長期間続くと、歯並びや噛み合わせに影響を及ぼす可能性が高くなります。
4~5歳を過ぎても指しゃぶりを続けている場合、歯科医院での専門的なアドバイスやサポートを受けることで、適切な対策を取ることが可能です。
1. 口腔内のチェックとリスク評価
歯科医師は、指しゃぶりによって生じる歯並びや噛み合わせの変化を診断することができます。特に以下のポイントを確認します。
- 前歯の傾き: 出っ歯(上顎前突)になっていないか
- 開咬の兆候: 上下の前歯が噛み合わず隙間ができていないか
- 顎の発達状態: 指しゃぶりによる顎の成長の偏りがないか
これらのチェックをもとに、現在の歯並びへの影響と、今後のリスクについて説明を受けることができます。
2. 子どもに適したアドバイス
歯科医師が直接、子どもに「指しゃぶりをやめることの大切さ」を伝えることも効果的です。
親が何度言っても聞き入れない場合でも、専門家である歯科医師からの言葉は子どもにとって信頼性があり、説得力を持ちやすいです。
例えば、
- 「このままだと、前歯がもっと前に出てきちゃうかもね」
- 「お口の中をきれいにするために、指しゃぶりを少しずつやめていこうね」
といった、子どもが理解しやすい言葉で説明してくれるため、本人も意識しやすくなります。
3. 親へのアドバイスと指導
親に対しても、子どもが無理なく指しゃぶりをやめられるように、具体的なアドバイスを提供します。例えば、
- 子どもの指しゃぶりの原因を理解する方法
- やめさせるために自宅でできる工夫
- どのような声かけをすると効果的か
など、家庭での対応についての具体的なアドバイスをもらうことができます。
・指しゃぶり防止の装置を使う方法
指しゃぶりがなかなかやめられない場合、歯科医院では指しゃぶりを防ぐための装置を提案することがあります。
これは、特に5~6歳を過ぎても指しゃぶりが続いている場合に検討される方法です。
1. 口腔内装置(プレオルソ・タングクリブ)
歯科医院で処方される装置の中には、「タングクリブ」や「プレオルソ」といった矯正装置があります。
これらの装置は、上顎の内側にワイヤーや樹脂製のストッパーを取り付けることで、指が口の中に入りにくくする仕組みになっています。
- タングクリブ: 上顎の内側にワイヤーを設置し、指が自然に入りにくいようにする装置
- プレオルソ: 取り外し可能なマウスピース型の装置で、指しゃぶりや口呼吸を防ぐ効果がある
これらの装置を使うことで、指しゃぶりの習慣を自然に減らし、無理なくやめることができるようにサポートします。
ただし、装置を使用する場合は、歯科医師と相談しながら適切な時期や方法を決めることが大切です。
2. 指に塗る苦味成分の活用
自宅でできる方法として、指に苦味成分が含まれた専用の塗料を塗る方法もあります。
これは、子どもが無意識に指をしゃぶったときに「苦い」と感じることで、指しゃぶりをやめるきっかけを作ることができます。
歯科医院では、安全性の高い専用の塗料を紹介してくれることもあるため、相談してみると良いでしょう。
ただし、無理に塗ると子どもがストレスを感じることがあるため、本人の意向を尊重しながら試すことが大切です。
・定期検診でのチェックポイント
指しゃぶりをやめた後も、定期的に歯科医院でのチェックを受けることが重要です。
指しゃぶりが長期間続いた場合、すぐに歯並びが元に戻るわけではなく、経過観察が必要になることがあります。
1. 歯並びや噛み合わせの確認
- 上顎前突(出っ歯): 前歯の傾きが自然に戻るか
- 開咬: 前歯の隙間が改善するか
- 下顎の成長: 適切に進んでいるか
これらを定期的に確認し、必要に応じて早めに矯正治療を検討することが大切です。
2. 舌の癖や口呼吸のチェック
- 発音の問題: 「サ行」や「タ行」の発音が不明瞭になっていないか
- 口の閉じ方: 口を閉じる習慣が定着しているか
- 舌の位置: 正しい位置にあるか
これらをチェックし、必要であれば舌のトレーニング(MFT:口腔筋機能療法)を取り入れることで、より正常な口腔機能を確立できます。
3. 必要に応じた矯正治療の提案
- 6~7歳頃にプレ矯正(マウスピース矯正など)を開始する
- 永久歯が生え揃ってから本格的な矯正治療を行う
指しゃぶりによる歯並びの影響は、早めに対応することで軽度の矯正で済むことが多いため、定期検診を欠かさないことが重要です。
指しゃぶりをやめた後のケアと経過観察

・歯並びの回復は自然にできる?
指しゃぶりをやめた後、歯並びは自然に元の状態に戻るのか気になるところです。
年齢や歯の状態によって、自然に回復する場合と矯正が必要な場合があります。
1. 幼児期にやめた場合は自然回復しやすい
3~4歳頃までに指しゃぶりをやめることができれば、多くの場合、歯並びは自然に回復しやすいです。
乳歯の段階では歯と歯の間に隙間(発育空隙)があり、成長とともに正しい位置へ戻りやすいからです。
ただし、指しゃぶりの影響で「出っ歯(上顎前突)」や「開咬(かいこう)」が進行している場合は、自然に回復しにくいことがあります。
特に、開咬の場合は、舌の位置や噛み合わせの習慣が影響するため、やめた後も意識的なトレーニングが必要になることがあります。
2. 5~6歳を過ぎた場合は注意が必要
5~6歳を過ぎて永久歯の生え変わりが始まる時期に指しゃぶりを続けていた場合、歯の位置が固定化されるため、自然回復が難しくなることがあります。
この場合、放置すると歯並びが悪化し、将来的に矯正治療が必要になる可能性が高まります。
歯並びの回復が期待できるかどうかのチェックポイント
- 指しゃぶりの影響で前歯が大きく前に傾いていないか
- 上下の前歯がしっかりと噛み合っているか
- 舌の動きに異常がないか(舌突出癖が残っていないか)
上記の問題が見られる場合は、矯正治療を検討するタイミングになります。
早めに歯科医院で相談し、適切なケアを受けることが重要です。
・噛み合わせや口腔習癖のチェック
指しゃぶりをやめた後でも、口腔内のバランスが崩れている場合は、噛み合わせのチェックや口腔習癖(舌の使い方・口呼吸など)の見直しが必要です。
1. 噛み合わせの異常の確認
- 開咬: 上下の前歯が噛み合わず隙間ができる
- 上顎前突: 出っ歯の状態
- 交叉咬合: 上の歯と下の歯が左右逆に噛み合う
噛み合わせが悪いと、食べ物をしっかり噛めなかったり、顎の成長に影響を与えたりするため、早期にチェックを受けることが大切です。
2. 舌の癖(舌突出癖)の改善
指しゃぶりの影響で、舌を前に突き出す「舌突出癖」が残ることがあります。これは、開咬や発音の問題につながるため、舌の位置を正しくするトレーニング(MFT:口腔筋機能療法)を取り入れると効果的です。
舌の癖を改善するためのポイント
- 舌を上顎につける練習をする
- ストローやガムを使って正しい舌の動きを意識する
- 口をしっかり閉じる習慣をつける
舌の位置が適切でないと、歯並びの問題が悪化することがあるため、定期的に歯科医師の指導を受けながら改善していくことが大切です。
3. 口呼吸の改善
指しゃぶりの影響で口を閉じる筋肉(口輪筋)が弱くなり、口呼吸の習慣が残ることがあります。
口呼吸は虫歯や歯肉炎のリスクを高めるだけでなく、顔の成長にも影響を与えるため、できるだけ早く改善することが望ましいです。
口呼吸を改善するための方法
- 口を閉じる筋肉を鍛える「あいうべ体操」を行う
- 鼻呼吸を意識し、寝るときに口テープを使う(医師に相談のうえ)
- 口周りの筋肉を鍛えるためによく噛んで食べる
・必要に応じた矯正治療の選択肢
指しゃぶりの影響で歯並びや噛み合わせに問題が残る場合、矯正治療を検討することが必要になることがあります。
特に、以下のような場合は矯正治療を考えるタイミングです。
- 指しゃぶりをやめても前歯の傾きが改善しない
- 噛み合わせが悪く、食事や発音に支障がある
- 口元のバランスが崩れている
1. マウスピース矯正(プレオルソ)
6~8歳頃の子どもに適したマウスピース型の矯正装置で、軽度の出っ歯や開咬の改善に効果があります。
取り外しができるため、食事や歯磨きの際にストレスが少ないのが特徴です。
2. ワイヤー矯正(本格矯正)
永久歯が生え揃った後(10歳以降)に行う矯正方法で、歯並びや噛み合わせの問題をしっかり改善することができます。
指しゃぶりの影響が大きく、自然回復が難しい場合には、専門医と相談しながら矯正治療を進めると良いでしょう。
3. 舌のトレーニング(MFT)と併用する矯正治療
矯正治療を進める際、舌の使い方や口周りの筋肉のバランスも同時に改善することが重要です。
そのため、MFT(口腔筋機能療法)を取り入れながら矯正を行うことで、より良い結果を得ることができます。
成功事例:指しゃぶりを卒業した子どもたちの変化

・指しゃぶりをやめた後に見られる口腔内の変化
指しゃぶりを卒業すると、口腔内にさまざまな良い変化が見られます。指しゃぶりが歯並びや噛み合わせに与える影響は大きいため、やめた後の経過観察が重要です。
1. 前歯の傾きが改善される可能性
指しゃぶりが原因で上の前歯が前に突出していた場合、やめた後に自然に後ろへ戻ることがあります。特に、乳歯の段階であれば、成長に伴い歯の位置が正常に近づく可能性が高いです。
ただし、永久歯に影響が及んでいる場合は、自然な回復が難しいことがあるため、歯科医のチェックが必要です。
2. 開咬(前歯が噛み合わない状態)の改善
指しゃぶりの影響で前歯の間に隙間ができていた場合、やめることで少しずつ改善することがあります。
特に、舌の位置や噛み方を意識することで、よりスムーズに噛み合わせが整うことが期待できます。
ただし、指しゃぶりによる開咬が長期間続いていた場合、舌の癖が残りやすく、舌突出癖がある場合は追加のトレーニングが必要になることもあります。
3. 口の周りの筋肉が正しく機能するようになる
指しゃぶりを続けていると、口を閉じる筋肉(口輪筋)が適切に発達しないため、口呼吸の習慣がつきやすくなります。
指しゃぶりを卒業すると、口元の筋肉のバランスが整い、自然と鼻呼吸がしやすくなることが期待されます。
・生活習慣や行動の変化
指しゃぶりを卒業すると、生活習慣にもポジティブな変化が見られることがあります。
1. 睡眠時のリラックス方法が変わる
指しゃぶりをすることで安心感を得ていた子どもは、代替の方法を見つけることでスムーズに眠れるようになります。
例えば、ぬいぐるみを抱く、寝る前にリラックスできるルーチンを作るなどの方法が自然と身についていきます。
2. 集中力の向上
指しゃぶりは無意識に行われることが多いため、やめることで手や口を使う別の活動に意識が向きやすくなります。
結果として、手遊びやお絵かき、ブロック遊びなどの細かい作業に集中できるようになり、発達の面でも良い影響を与えることがあります。
3. 人前での行動に自信が持てる
ある程度の年齢になると、指しゃぶりが恥ずかしいと感じるようになる子もいます。
指しゃぶりをやめることで、「お兄さん・お姉さんになれた」という自信がつき、友達とのコミュニケーションにも前向きになるケースがあります。
・指しゃぶりをやめた後の口腔ケアとフォローアップ
指しゃぶりを卒業した後も、定期的なチェックとケアを続けることが大切です。
1. 定期的な歯科検診で歯並びをチェック
指しゃぶりをやめた後の歯並びの変化は、個人差があります。
特に、前歯の位置や噛み合わせがしっかりと改善されているかを確認するために、歯科医の定期検診を受けることが推奨されます。
2. 口周りの筋肉トレーニング(MFT)を取り入れる
指しゃぶりをしていた子どもは、舌の使い方や口の動かし方に癖が残ることがあります。
これを改善するためには、MFT(口腔筋機能療法)を取り入れ、舌や口の周りの筋肉を正しく使うトレーニングを行うことが効果的です。
トレーニングの例
- 舌を正しい位置に置く練習
- 口を閉じる習慣を意識する
- ストローを使った舌の動かし方トレーニング
3. 食事の際にしっかり噛む習慣をつける
指しゃぶりをしていた子どもは、噛み合わせが安定していないことがあるため、硬めの食べ物を意識して食べることで、しっかりと噛む習慣をつけることが大切です。
よく噛むことで顎の発達が促され、歯並びや噛み合わせの改善にも役立ちます。
指しゃぶりをやめることで得られる長期的なメリット

・歯並びと噛み合わせの健全な発育
指しゃぶりをやめることにより、歯並びや噛み合わせの発育に大きなメリットがあります。特に幼少期に指しゃぶりをやめることで、自然な歯列の成長を促し、将来的な歯科矯正の必要性を減らすことができます。
1. 上顎前突(出っ歯)のリスク軽減
指しゃぶりが長く続くと、前歯が前方に押し出されるため、上顎前突(出っ歯)の状態になることがあります。しかし、指しゃぶりをやめることで、この影響を最小限に抑え、自然な歯の位置を維持しやすくなります。
特に乳歯の段階で指しゃぶりをやめることができれば、成長とともに前歯の傾きが自然に改善する可能性が高いため、できるだけ早期にやめることが理想です。
2. 正しい噛み合わせの確立
指しゃぶりによる開咬(上下の前歯が噛み合わない状態)は、食事の際に噛み切る力が弱くなり、消化機能に影響を及ぼすことがあります。指しゃぶりをやめることで、噛み合わせが適切に整い、食事の際にしっかりと咀嚼できるようになるため、消化吸収の向上にもつながります。
3. 顎の正常な発育を促す
指しゃぶりを続けると、指が口の中で上顎を押し上げる力がかかり、上顎が狭くなったり、下顎の発育が抑制されたりすることがあります。指しゃぶりを卒業することで、顎の成長が適切に進み、将来的な噛み合わせの問題を防ぐことができます。
・健康的な呼吸習慣の定着
指しゃぶりをしていると、口が開いたままの状態が続きやすくなり、口呼吸の習慣がつきやすくなります。指しゃぶりをやめることで、鼻呼吸が定着し、さまざまな健康面でのメリットが得られます。
1. 口腔内の健康維持(虫歯・歯肉炎の予防)
口呼吸が習慣化すると、口の中が乾燥しやすくなり、唾液の分泌量が減少することで、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。しかし、指しゃぶりをやめて鼻呼吸が定着すると、唾液がしっかりと分泌されるようになり、口腔内の自浄作用が向上し、虫歯や歯周病の予防につながります。
2. 風邪やアレルギーの予防
鼻呼吸には、空気中のホコリや細菌を取り除くフィルターの役割があり、風邪やアレルギーを予防する効果があります。指しゃぶりをやめて口を閉じる習慣がつくことで、免疫機能が向上し、風邪を引きにくくなることが期待できます。
3. 睡眠の質の向上
口呼吸をしていると、寝ている間に喉が乾燥しやすく、いびきや無呼吸症候群のリスクが高まります。指しゃぶりを卒業し、口をしっかり閉じて寝る習慣がつくことで、より深い睡眠を得られるようになり、日中の集中力や体調管理にも良い影響を与えます。
・顔の発育と発音の改善
指しゃぶりが続くと、顔の成長バランスや発音に影響を及ぼすことがあります。指しゃぶりをやめることで、口元の筋肉の発達が正常化し、正しい顔の発育や発音の形成が促されます。
1. 口周りの筋肉のバランスが整う
指しゃぶりを続けると、口を閉じる力が弱まり、口元が緩んだ印象になりやすくなります。しかし、指しゃぶりをやめることで、口輪筋や頬の筋肉が適切に発達し、自然な口元の引き締まりが生まれます。
2. 発音が明瞭になる
指しゃぶりを続けると、舌の位置が正しく機能せず、「サ行」や「タ行」の発音が不明瞭になることがあります。指しゃぶりを卒業すると、舌の動きが自然になり、正しい発音ができるようになります。
3. 顔のバランスが整う
長期間の指しゃぶりが続くと、上顎が狭くなったり、下顎が後退したりすることで、顔のバランスが崩れることがあります。指しゃぶりをやめることで、自然な顎の発育が促され、将来的な顔の形が整いやすくなります。
・指しゃぶりを卒業することの総合的なメリット
指しゃぶりをやめることで、歯並びの改善、健康的な呼吸の確立、正しい顔の発育、発音の向上など、多くのメリットが得られます。
- 歯並びの改善と噛み合わせの安定
- 出っ歯や開咬のリスクを軽減
- 顎の発育を正常に促進
- 口呼吸の予防と健康維持
- 口腔内の健康維持(虫歯・歯肉炎のリスク軽減)
- 鼻呼吸の定着による風邪やアレルギーの予防
- 顔のバランスと発音の向上
- 口周りの筋肉の発達促進
- 明瞭な発音の確立
指しゃぶりをやめることで、子どもの成長に良い影響を与え、将来的な歯科矯正の必要性を減らすこともできます。歯科医院と相談しながら、適切なタイミングで指しゃぶりを卒業できるようサポートすることが、健康的な成長につながる大切なステップです。
監修:愛育クリニック麻布歯科ユニット
所在地〒:東京都港区南麻布5丁目6-8 総合母子保健センター愛育クリニック
電話番号☎:03-3473-8243
*監修者
愛育クリニック麻布歯科ユニット
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会
カテゴリー:コラム 投稿日:2025年2月28日

