子どもの歯の数が足りない? 先天性欠如のチェック方法と対応
子どもの歯が生えそろわない…これって普通?
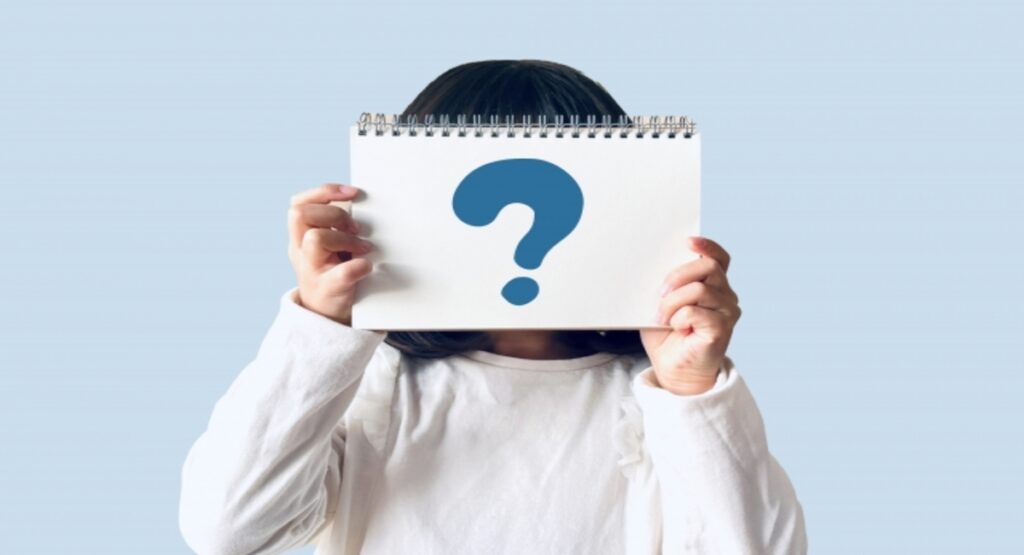
乳歯と永久歯の生え変わりの基本サイクル
人間の歯は、赤ちゃんのときに生えてくる「乳歯」と、その後に生え変わる「永久歯」の2種類があります。
乳歯の生え方
乳歯は、生後6ヶ月頃から生え始め、3歳頃までに合計20本がそろいます。
生える順番には個人差がありますが、一般的には下の前歯(下顎中切歯)から生え始め、次に上の前歯(上顎中切歯)が続きます。
その後、奥歯や犬歯が順番に生え、最後に第二乳臼歯(奥歯)が生えることで乳歯の生えそろいが完了します。
永久歯への生え変わり
永久歯の生え変わりは、6歳頃から12歳頃にかけて徐々に進みます。
最初に生えてくるのは「6歳臼歯(第一大臼歯)」と呼ばれる奥歯で、次いで前歯が乳歯から永久歯に生え変わります。
最後に第二大臼歯が生え、親知らず(第三大臼歯)が20歳前後で生えてくることもあります。
この生え変わりのスケジュールには個人差があり、前後することも珍しくありません。しかし、通常の生え変わりの時期を過ぎても永久歯が生えてこない場合は、専門的な診察が必要になるケースもあります。
生え変わりが遅れる理由と個人差について
子どもの歯の生え変わりが遅れる原因はさまざまですが、大きく分けて「正常な範囲の遅れ」と「注意が必要な遅れ」に分類できます。
正常な範囲の遅れ
以下のような理由で、一時的に生え変わりが遅れることがあります。
- 遺伝的要因:親御さんが歯の生え変わりが遅かった場合、子どもも同様に遅くなる傾向があります。
- 体質や成長速度の違い:身体の発育がゆっくりなお子さんは、歯の生え変わりも遅くなることがあります。
- 噛む刺激の不足:柔らかい食事が多いと顎の発育が遅れ、歯の生え変わりがスムーズに進まないことがあります。
注意が必要な遅れ
生え変わりの遅れが極端な場合や、特定の歯がなかなか生えてこない場合は、何らかの問題が隠れている可能性があります。
- 乳歯が抜けても永久歯が生えてこない:先天性欠如の可能性が考えられます。
- 乳歯が抜ける前に永久歯が生えてしまう:「二重歯列(シャークトゥース)」と呼ばれる状態で、矯正治療が必要になる場合があります。
- 顎の発育が遅い:歯が生えてくるスペースが足りず、永久歯の生え変わりが遅れることがあります。
これらの場合は、歯科医院での診察を受けることが重要です。
「歯の数が足りない」可能性があるケースとは
子どもの歯が通常のスケジュールで生え変わらない場合、「先天性欠如」が原因の可能性があります。
先天性欠如とは?
先天性欠如とは、生まれつき永久歯の一部が欠如している状態を指します。通常、永久歯は28本(親知らずを含めると32本)生えてきますが、先天的に特定の歯が存在しない場合、生え変わりがスムーズに進まず、「乳歯が抜けても次の歯が生えてこない」といった症状が見られます。
先天性欠如が疑われるサイン
- 乳歯の時点で本数が少ない(通常20本あるはずの乳歯が少ない)
- 乳歯が抜けてもなかなか永久歯が生えてこない
- 歯科検診で永久歯の「歯胚(歯の元となる組織)」が確認できない
放置するとどうなる?
先天性欠如をそのまま放置すると、咬み合わせの不具合や顎の成長への影響が生じる可能性があります。
例えば、前歯が足りない場合、発音に影響を及ぼすことがあり、奥歯の欠如は食べ物をうまく噛めない原因となります。
先天性欠如とは?歯が生まれつき足りない状態

先天性欠如とは?発生のメカニズム
先天性欠如とは、生まれつき特定の永久歯が存在しない状態を指します。通常、永久歯は乳歯が抜けるとその下から生えてくるものですが、先天性欠如の場合、歯のもととなる「歯胚(しはい)」が発育せず、永久歯が作られないため、生えてこないという特徴があります。
この現象は、発生の過程で何らかの要因により歯の形成が阻害されることが原因と考えられています。歯は胎生6週目頃から形成が始まり、乳歯とともに永久歯の歯胚も同時に作られます。しかし、歯胚が形成されなかった場合、乳歯が抜けても次の歯が生えてこない状態となり、結果的に歯の本数が足りなくなります。
先天性欠如は特定の遺伝的要因や環境的要因によって引き起こされると考えられており、家族内で同じ歯が欠如するケースも報告されています。また、成長ホルモンの分泌異常や胎児期の発育障害、栄養不足などが関係する可能性も指摘されていますが、正確なメカニズムはまだ完全には解明されていません。
先天性欠如がある場合、乳歯が長く残ることが多いですが、乳歯もいずれは寿命が来て抜けてしまいます。そのため、将来的に噛み合わせや顎の発育に影響を及ぼすことがあるため、早めの診断と対応が重要です。
どの歯に起こりやすい?よく見られる部位
先天性欠如はすべての永久歯に発生する可能性がありますが、特に特定の歯に多く見られる傾向があります。先天性欠如が起こりやすい歯として、以下の部位が挙げられます。
- 下顎の第二小臼歯(前から5番目の歯)
- 上顎の側切歯(前歯の両側にある歯)
- 第三大臼歯(親知らず)
下顎の第二小臼歯の欠如は、先天性欠如の中でも特に発生頻度が高いとされており、噛み合わせへの影響が大きいため、注意が必要です。この歯が欠如していると、上下の噛み合わせがずれたり、隣の歯が移動してしまったりすることがあります。
上顎の側切歯の欠如は、前歯の見た目に関わるため、審美的な問題を引き起こしやすいです。側切歯がない場合、隣の歯(犬歯)が移動し、前歯の歯並びが乱れることが多く、矯正治療が必要になるケースがよくあります。
第三大臼歯(親知らず)の欠如は、比較的よく見られるもので、医学的には特に問題視されないことが多いです。親知らずはそもそも噛み合わせに大きな影響を与えない場合が多く、欠如していても特に治療の必要はありません。
また、まれに乳歯段階で歯の本数が足りないケースもあり、この場合は永久歯にも欠如が見られる可能性が高いため、早めの歯科検診で診断を受けることが推奨されます。
遺伝や環境要因との関係
先天性欠如は、遺伝的な要因と環境的な要因の両方が関与していると考えられています。
遺伝的要因
- 家族内で同じ歯が欠如しているケースが多く報告されています。例えば、親が先天性欠如で特定の歯が足りない場合、その子どもにも同じ部位で欠如が見られることがあります。
- 遺伝的な影響は、特に第二小臼歯や側切歯の欠如に関して顕著であり、兄弟姉妹の中で同じ歯が欠如するケースも珍しくありません。
- 先天性欠如が起こる確率は、日本人では約10%前後とされており、比較的多く見られる現象です。
環境要因
- 胎児期の発育異常や母体の健康状態が影響することがあります。例えば、妊娠中の栄養状態や薬の服用、ホルモンバランスの乱れなどが歯の形成に影響を及ぼす可能性があります。
- 乳幼児期の栄養不足も関係すると考えられており、カルシウムやビタミンDの不足が歯の形成に影響を与えることがあります。
- 歯の発育が進む時期に、大きな病気や発熱を繰り返していた場合、一部の歯の発育に影響を与えることもあると考えられています。
遺伝と環境の相互作用
すべての先天性欠如が遺伝だけで決まるわけではなく、環境要因が重なることで発症するケースもあります。
例えば、遺伝的に先天性欠如のリスクを持つ子どもが、胎児期や幼少期に何らかの外的要因にさらされた場合、歯の発育が阻害される可能性が高まると考えられています。
先天性欠如の診断と対応
歯科医院では、X線(レントゲン)やCTを用いて、永久歯の歯胚があるかどうかを確認することで診断を行います。
早期発見が重要であり、歯科検診を定期的に受けることで、欠如している歯の有無やその影響を適切に判断できます。
どうやってチェックする?自宅でできる確認方法

乳歯の本数を数えるポイント
子どもの歯の生え方に異変がないかを確認するためには、まず乳歯の本数を正しく数えることが大切です。通常、乳歯は上下合わせて20本あります。生後6カ月頃から生え始め、3歳頃までにすべての乳歯が生えそろうのが一般的です。
乳歯の本数を数える手順
- 子どもを明るい場所で座らせる
歯の本数を確認するには、口の中をしっかりと見る必要があります。明るい場所で、できれば自然光の下で行うと見やすくなります。 - 上の歯と下の歯に分けて本数を数える
乳歯は上10本、下10本の計20本が基本です。前歯から順に数えていくと数え間違いを防げます。 - 歯と歯の間に隙間があるかを確認する
乳歯の間にはある程度の隙間があるのが正常ですが、極端に隙間が広い、または反対にギュウギュウに詰まっている場合は歯並びに影響する可能性があります。 - 左右対称に歯が生えているかをチェックする
通常、乳歯は左右対称に生えるため、一方に歯があるのにもう一方に同じ歯がない場合は注意が必要です。
乳歯が足りない場合のサイン
- 3歳を過ぎても明らかに本数が少ない
- 上の歯と下の歯の本数が左右で大きく違う
- 永久歯が生える時期になっても乳歯が抜けない
これらの兆候が見られる場合は、先天性欠如の可能性もあるため、早めに歯科医院で相談することが重要です。
生え変わりのタイミングで気をつけること
乳歯から永久歯への生え変わりは、通常6歳頃から12歳頃にかけて行われます。この時期に注意すべきポイントを理解しておくことで、先天性欠如を早期に発見できる可能性が高まります。
永久歯の生え変わりの流れ
- 6歳頃:「6歳臼歯(第一大臼歯)」が最初に生える
一番奥に生えてくるこの歯は永久歯の中でも特に重要な歯です。生えてくるかどうかをしっかり確認しましょう。 - 7~8歳頃:前歯(中切歯・側切歯)の生え変わり
下の前歯(中切歯)が抜けて永久歯が生えてくるのが一般的ですが、この時期になっても生えてこない場合は、レントゲンで歯胚の有無を確認する必要があります。 - 9~12歳頃:犬歯・小臼歯・第二大臼歯の生え変わり
10歳を過ぎても小臼歯(前から4番目・5番目の歯)が生えてこない場合は、先天性欠如の可能性が高まります。
生え変わりが遅れる場合の注意点
- 乳歯が抜けたのに永久歯がなかなか生えてこない
- 反対側の歯は生えているのに片側だけ生えない
- 周りの同年代の子どもより明らかに生え変わりが遅い
生え変わりが遅れる理由はいくつかありますが、特定の歯が欠如している場合は、適切な治療を検討する必要があります。
歯科医院での診断の重要性
自宅でのチェックも大切ですが、最も確実なのは歯科医院でのレントゲン診断です。先天性欠如が疑われる場合は、以下のような流れで診断が行われます。
1. 問診と視診
まず、歯科医が口の中を確認し、乳歯の本数や生え変わりの進行状況をチェックします。また、親御さんに家族内で歯が足りない人がいるかどうかを尋ねることもあります。
2. レントゲン撮影(X線検査)
永久歯の歯胚が形成されているかを確認するために、レントゲンを撮影します。これにより、見た目では分からない「埋伏歯(骨の中に埋まったままの歯)」や「先天性欠如の歯」を診断できます。
3. 診断結果の説明と治療方針の決定
- 歯が埋まっている場合:矯正治療などで歯を誘導する方法を検討する
- 先天性欠如がある場合:矯正治療、ブリッジ、インプラントなどの選択肢を提案
歯科検診を受ける適切な時期
- 3歳児検診・5歳児検診:乳歯の本数や生え方をチェック
- 6歳以降の定期検診:永久歯の生え方を確認し、欠如がないかチェック
- 生え変わりの遅れが気になる場合はすぐに受診
歯科医院での早期発見によって、適切な治療や対応を行うことができます。
先天性欠如の影響とは?放置するとどうなる?

咬み合わせのズレによる影響
先天性欠如によって特定の歯が生えてこない場合、咬み合わせ(噛み合わせ)のバランスが崩れやすくなります。特に、奥歯の小臼歯(4番目・5番目の歯)や前歯(側切歯)が欠如していると、周囲の歯がそのスペースを埋めようと移動し、咬み合わせのズレが生じることがあります。
咬み合わせがズレる原因
- 隣の歯が倒れ込んでくる
欠如した歯のスペースに隣の歯が移動してしまうと、正常な咬み合わせを維持できなくなります。 - 対合歯(反対側の歯)が伸びてくる
上下の歯は噛み合うことで適切な位置を保っています。しかし、例えば下の歯が欠如している場合、噛み合うはずの上の歯が伸びてきてしまい、歯並び全体のバランスが崩れることがあります。 - 噛む力のバランスが崩れる
歯が足りないことで、一部の歯に過剰な負担がかかりやすくなります。本来の噛む機能が損なわれ、特定の歯だけがすり減ったり、将来的に顎関節症を引き起こすリスクも高まります。
咬み合わせのズレが引き起こす問題
- 食べ物をしっかり噛めず、消化不良を起こしやすい
- 顎の筋肉に負担がかかり、顎関節症のリスクが高まる
- 歯並びが崩れ、見た目のバランスも悪くなる
特に成長期の子どもは、顎の発育とともに咬み合わせも変化します。そのため、放置することで歯列不正が進行し、より複雑な矯正治療が必要になることもあります。
見た目や発音への影響
先天性欠如の影響は、機能面だけでなく、見た目(審美面)や発音にも大きく関わります。
見た目への影響
- 前歯の側切歯が欠如すると、前歯の隙間が目立ち、審美的な問題が生じる
- 上の歯が少ないと、笑ったときに歯並びが不均衡に見える
- 咬み合わせのズレによって、顔の歪みが生じることがある
特に前歯の先天性欠如は、笑ったときや話すときに目立ちやすく、コンプレックスを抱える子どもも少なくありません。見た目に影響を及ぼすことで、自信を失い、笑うことを避けるようになるケースもあります。
発音への影響
歯の位置や本数は、正しい発音をする上で重要な役割を果たします。特に、前歯の欠如がある場合、以下のような発音の問題が起こりやすくなります。
- サ行やタ行の発音が不明瞭になる
前歯がないと、舌が正しい位置に当たらず、空気が漏れて発音が不明瞭になることがあります。 - 滑舌が悪くなり、話しづらさを感じる
歯がないことで、舌の位置が安定せず、言葉をはっきり発音しづらくなることがあります。 - 息漏れが起こり、発話に影響を与える
前歯がないと、息がスムーズにコントロールできず、発音のリズムが乱れることがあります。
こうした発音の問題は、学校生活や人間関係に影響を与えることもあります。発音の矯正が必要な場合もあるため、早めの対応が求められます。
顎の発育への影響
子どもの成長期において、歯の本数は顎の発育にも大きな影響を与えます。先天性欠如によって特定の歯が欠如していると、顎の正常な成長が妨げられる可能性があります。
顎の発育に及ぼす影響
- 噛む刺激が不足し、顎の発達が遅れる
子どもは歯を使ってしっかり噛むことで、顎の骨を発達させます。しかし、歯が足りないと噛む力がうまく分散されず、顎の成長が遅れることがあります。 - 片側ばかりで噛む癖がつき、顎が歪む
片側の歯が欠如していると、反対側の歯ばかりで噛む癖がつきやすくなります。これにより、顎のバランスが崩れ、顔の非対称が生じることがあります。 - 顎の骨が十分に成長せず、将来の歯並びに影響を与える
顎の骨が十分に成長しないと、残っている歯が本来の位置に収まらず、歯並びが乱れる原因となります。
顎の発育を促すためにできること
- 欠如した歯がある場合でも、しっかり噛む習慣を身につける
- 歯科医院で顎の成長に合わせた治療を受ける
- 必要に応じて矯正治療を検討する
顎の発育は、将来的な歯並びや咬み合わせに直結するため、放置せずに適切な治療を行うことが重要です。
どんな治療が必要?対応方法を解説

矯正治療でスペースを調整する方法
先天性欠如がある場合、まず考えられる治療のひとつが矯正治療です。永久歯が生えてこないことで歯並びにスペースができてしまうと、隣の歯が倒れ込んだり、噛み合わせがずれてしまうことがあります。矯正治療によってスペースを適切に調整し、将来的な歯並びの乱れを防ぐことが可能です。
矯正治療の目的
- 歯並びを整え、噛み合わせを調整する
- 欠如した歯のスペースを広げたり、閉じたりする
- 顎の成長をコントロールし、左右のバランスを整える
矯正治療の方法
- スペースを閉じる矯正
欠如した歯のスペースを、隣の歯を移動させることで埋める方法です。特に、前歯や側切歯が欠如している場合に選択されることが多いです。 - スペースを維持する矯正
欠如した歯の部分に、将来的にインプラントやブリッジを入れる予定がある場合、スペースを維持するために矯正を行います。この場合、保隙装置(スペース・メンテイナー)を使用して、歯が倒れ込むのを防ぎます。 - 顎の成長を利用した矯正
子どもの成長期であれば、顎の発育をコントロールしながら矯正を行うことで、欠如歯の影響を最小限に抑えることができます。
矯正治療の開始時期
- 6歳頃:顎の成長に合わせて早期矯正を開始することが可能
- 10歳~12歳:生え変わりの時期に合わせた本格的な矯正治療が可能
- 成人以降:欠如した歯のスペースを調整し、補綴治療(インプラントやブリッジ)と組み合わせた矯正治療が可能
矯正治療の計画は、歯の欠如の部位や本数、顎の発育状態によって異なるため、専門の矯正歯科で相談することが重要です。
ブリッジやインプラントの適応について
矯正治療だけではスペースを補えない場合、補綴治療(歯を補う治療)が必要になることがあります。主な方法としては、ブリッジやインプラントが挙げられます。
ブリッジ治療とは?
ブリッジとは、欠如している歯の両隣の歯を支えにして、人工の歯を固定する治療法です。
メリット
- 短期間で治療が完了する(2~3回の通院で可能)
- 違和感が少なく、見た目も自然
- 保険適用のブリッジもあり、費用を抑えられる
デメリット
- 両隣の健康な歯を削る必要がある
- 長期間使用すると、支えの歯に負担がかかる
- 欠如した部位によっては適応できないこともある
インプラント治療とは?
インプラントは、顎の骨に人工歯根(チタン製のネジ)を埋め込み、その上に人工歯を取り付ける治療方法です。
メリット
- 自然な見た目で、自分の歯と同じように噛むことができる
- 周囲の健康な歯に負担をかけない
- 長期的に安定した機能を維持できる
デメリット
- 外科手術が必要であり、治療期間が長い(約3~6カ月)
- 顎の骨が十分に成長している必要があるため、子どもには適応できない
- 費用が高額(保険適用外の場合が多い)
どちらを選ぶべき?
- 子ども(成長途中)の場合 → 一時的にブリッジや矯正で対応し、成人後にインプラントを検討
- 成人(顎の成長が完了している場合) → インプラントが最適な選択肢
最適な治療法は、年齢・顎の発育状況・費用・希望する見た目などによって異なるため、歯科医師と相談しながら決定することが重要です。
小児歯科や矯正専門医と連携した治療
先天性欠如の治療は、一般歯科だけでなく、矯正歯科や小児歯科との連携が重要です。適切なタイミングで適切な治療を受けるために、歯科医師と綿密な相談を行いましょう。
小児歯科での対応
- 乳歯の段階で欠如の有無をチェック
- 永久歯が生えてくるタイミングを管理し、異常があれば早期に対応
- 成長期に合わせた矯正治療のプランを立てる
矯正専門医との連携
- 欠如している歯の影響を最小限にするために、矯正治療を適切に開始
- スペースを維持または調整し、将来の治療(インプラント・ブリッジ)に備える
補綴専門医との連携
- 成人後の補綴治療(インプラント・ブリッジ)の計画を立てる
- 長期的なメンテナンスを考慮した治療選択
総合的な治療の流れ
- 幼少期(6歳頃) → 乳歯の欠如がないか確認し、必要に応じて矯正の準備
- 学童期(10歳~12歳) → 矯正治療でスペースを調整
- 成人後(18歳以降) → インプラントやブリッジで最終的な補綴治療を実施
適切な治療計画を立て、成長とともに最適な方法を選択していくことが大切です。
矯正はいつ始めるべき?年齢別の治療アプローチ

乳歯期~混合歯列期にできる対応
乳歯期から混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)にかけて、先天性欠如の早期発見と対応が重要になります。この時期に適切な対応を行うことで、将来的な矯正治療や補綴治療の選択肢が広がり、より理想的な歯並びを実現しやすくなります。
乳歯期(0~6歳)での対応
乳歯期には、歯科検診を通じて先天性欠如の可能性を早期に見つけることが大切です。通常、3歳頃までに乳歯が生えそろいますが、本数が明らかに少ない場合、永久歯にも欠如がある可能性が高くなります。
乳歯期に行うべきこと
- 3歳児検診で乳歯の本数を確認する
- 歯科医院での定期検診を受ける(半年~1年に1回)
- 噛む習慣を意識し、顎の成長を促す食事を取り入れる
乳歯期では、基本的に治療は行わず、永久歯の発育状況を慎重に観察します。ただし、歯の欠如によって顎の成長に影響が出る可能性があるため、噛む力を育むことが大切です。
混合歯列期(6~12歳)での対応
この時期は、乳歯が抜け、永久歯へと生え変わる重要な時期です。先天性欠如がある場合、歯列のバランスが崩れやすいため、歯科矯正の開始を検討することが推奨されます。
混合歯列期の矯正の目的
- 欠如している歯のスペースを適切に管理する
- 周囲の歯が倒れ込むのを防ぐ
- 顎の発育をコントロールし、理想的な歯並びを確保する
具体的な矯正方法
- 保隙装置(スペース・メンテイナー)
欠如している歯のスペースを維持するための装置を使用し、隣の歯が移動するのを防ぐ。 - 部分矯正(リテーナーや拡大装置の使用)
欠如している部位のスペースを確保したり、閉じたりするために、部分的な矯正を行う。 - 顎の成長をコントロールする機能矯正
出っ歯や受け口など、噛み合わせのズレを修正しながら、歯の欠如が与える影響を最小限にする。
混合歯列期に適切な矯正治療を行うことで、成人後の治療負担を軽減し、より理想的な歯並びを実現しやすくなります。
永久歯列が完成するまでの治療計画
永久歯列期(12歳~18歳)では、すべての永久歯が生えそろい、最終的な矯正や補綴治療の選択を行います。
この時期の治療の目的
- 欠如した歯のスペースを閉じる or 維持するかを決定
- 補綴治療(ブリッジやインプラント)の準備を行う
- 最終的な歯並びを整え、噛み合わせを最適化する
具体的な治療の選択肢
- 矯正装置(ブラケット・マウスピース)を使って歯並びを調整
欠如している歯のスペースを閉じたり、調整したりするために本格的な矯正を実施。
マウスピース型矯正(インビザライン)を選択することも可能。 - スペースが確保されている場合、インプラントやブリッジを検討
永久歯列が完成すると、欠如している歯の代替として補綴治療を行うことができる。
骨の成長が十分でない場合、インプラントの準備段階としてスペースを維持することもある。
永久歯列期の治療は、最終的な仕上げの段階にあたるため、慎重に治療計画を立てることが大切です。
早期発見・早期治療のメリット
先天性欠如は、早めに発見し、適切な対応をすることで、将来的な影響を最小限に抑えることができます。
早期発見のメリット
- 咬み合わせのズレを防ぎ、理想的な歯並びを確保できる
- 矯正治療を行うことで、補綴治療(ブリッジやインプラント)の選択肢が広がる
- 顎の発育をコントロールし、顔のバランスを整えることができる
早期治療を行わなかった場合のリスク
- 歯の欠如部分に周囲の歯が倒れ込み、スペースがなくなる
- 噛み合わせが乱れ、顎関節症や発音の問題を引き起こす
- 将来的な補綴治療が複雑になり、治療期間が長引く
早期に矯正治療を始めることで、歯列を整え、最終的な治療の選択肢を増やすことができます。
子どもの負担を減らすために親ができること

定期検診の重要性
先天性欠如のある子どもが健やかな歯の発育を迎えるためには、定期的な歯科検診が欠かせません。永久歯が生えてこないことで歯列や噛み合わせに影響を及ぼすため、早期発見・早期対応が非常に重要です。
なぜ定期検診が必要なのか?
- 欠如歯の進行状況をモニタリングできる
先天性欠如は、乳歯の段階では気づかれにくいことがあります。定期検診を受けることで、永久歯の歯胚の有無を確認でき、欠如がある場合は治療計画を立てることが可能になります。 - 噛み合わせのズレを防ぐことができる
欠如した歯のスペースを放置すると、隣の歯が傾いたり、対合歯が伸びてきたりすることで、噛み合わせのバランスが崩れることがあります。定期検診で早めに対策を取ることで、これを防ぐことができます。 - 子どもの成長に合わせた治療ができる
成長期に合わせた矯正治療やスペース維持のための装置を適切な時期に使用することで、将来的な負担を軽減できます。
定期検診の頻度と内容
- 3歳児検診・5歳児検診:乳歯の本数や歯並びをチェック
- 6歳以降の定期検診(半年に1回):永久歯の生え方、欠如の有無、噛み合わせの状態を確認
- 矯正治療中は1~3カ月ごとに診察
定期的な歯科検診を受けることで、欠如している歯の管理や将来的な治療の選択肢を増やすことができます。
口腔内の成長を見守るポイント
子どもの口腔内の成長を見守ることは、親にとって重要な役割です。特に、先天性欠如がある場合、歯の本数が少ないことによる咀嚼機能の低下や、顎の発育への影響を最小限に抑えるための工夫が必要です。
家庭でできるチェックポイント
- 歯の本数を定期的に数える
乳歯期から混合歯列期にかけて、上下20本の乳歯がきちんと揃っているか、永久歯が適切に生えているかを確認しましょう。 - 生え変わりのタイミングを観察する
片側だけ永久歯が生えてこない、抜けたまま何カ月も経っている場合は、先天性欠如の可能性を考慮し、歯科医師に相談することが大切です。 - 噛み合わせを意識する
食事中に片側ばかりで噛んでいないか、噛みづらそうにしていないかを観察することで、顎の成長や歯並びの異常に気づくことができます。 - 発音や滑舌の変化をチェックする
前歯の欠如がある場合、サ行やタ行の発音が不明瞭になることがあります。お子さんの発音に変化が見られたら、歯科医師に相談しましょう。 - 口呼吸になっていないか確認する
先天性欠如があると、口腔周囲の筋肉バランスが崩れ、口呼吸の癖がつくことがあります。口が開きっぱなしになっていないかを注意し、必要に応じて鼻呼吸のトレーニングを取り入れましょう。
家庭での簡単なチェックを続けることで、早期に異常を発見し、適切な対応を取ることができます。
歯科医院選びのポイント
先天性欠如の治療は、一般歯科だけでなく矯正歯科や小児歯科の専門的な診察が必要となる場合があります。適切な治療を受けるために、どのような歯科医院を選ぶべきかを知っておくことが大切です。
良い歯科医院の選び方
- 小児歯科・矯正歯科に対応しているか
先天性欠如がある場合、矯正治療が必要になるケースが多いため、小児歯科や矯正歯科と連携している歯科医院を選ぶことが重要です。 - 先天性欠如の治療実績があるか
歯科医院のホームページや口コミなどで、先天性欠如に関する治療経験があるかを確認しましょう。 - レントゲンやCT撮影が可能か
歯の欠如を診断するには、レントゲンやCT撮影が必要となるため、これらの設備が整っている医院を選ぶことが望ましいです。 - 子どもがリラックスできる環境が整っているか
歯科医院が苦手な子どもでも通いやすいように、キッズスペースがある、スタッフが子どもの扱いに慣れているといったポイントも重要です。 - 治療計画を明確に説明してくれるか
先天性欠如の治療は、成長に合わせて長期間にわたることが多いため、今後の見通しを分かりやすく説明してくれる歯科医院を選びましょう。
歯科医院とのコミュニケーションが大切
- 疑問点を気軽に相談できる環境を整える
- 子ども自身が納得できるよう、歯科医師が優しく説明してくれるかを確認する
- 治療の選択肢やリスクについて、しっかり話し合えるかを見極める
適切な歯科医院を選ぶことで、子どもの負担を最小限に抑えながら、最良の治療を受けることができます。
先天性欠如がある子どもが快適に過ごすための工夫

食事で気をつけること
先天性欠如がある子どもは、噛み合わせのバランスが崩れたり、咀嚼がしにくくなったりすることがあります。そのため、食事の際に工夫をすることで、食べやすさを向上させ、顎の成長や消化の負担を軽減できます。
食事のポイント
- 硬すぎず、柔らかすぎない食材を選ぶ
歯が足りないと、噛む力のバランスが崩れ、片側だけで噛む癖がつくことがあります。
ある程度の硬さがあり、噛むトレーニングができる食材(根菜類や海藻、繊維質の多い野菜)を取り入れましょう。
ただし、硬すぎる食べ物(するめ・硬いナッツ類)は避け、歯や顎に過度な負担をかけないようにすることも大切です。 - 食材を小さく切って、食べやすくする
歯の欠如があると、うまく噛み切れずに食べこぼしが増えることがあります。
野菜や肉は細かくカットし、食べやすい形状にするとストレスなく食事ができます。 - 左右バランスよく噛む習慣をつける
先天性欠如があると、片側でばかり噛む癖がつきやすくなります。
片側だけで噛むことが続くと、顔の歪みや顎関節症のリスクが高まるため、「右で5回、左で5回」といったバランスを意識させると良いでしょう。 - カルシウム・ビタミンDを積極的に摂取する
骨や歯の発育には、カルシウムやビタミンDが欠かせません。
カルシウムを多く含む食品:牛乳、チーズ、小魚、豆腐、ほうれん草
ビタミンDを多く含む食品:鮭、きのこ類、卵
食事の工夫をすることで、歯が足りないことによる負担を軽減し、子どもが快適に食事を楽しめるようになります。
発音のトレーニング方法
歯は発音にも大きく関わるため、先天性欠如があると一部の音が発音しにくくなることがあります。特に、前歯(側切歯や中切歯)が欠如している場合、サ行・タ行・ナ行・ラ行の発音が不明瞭になることがあります。
発音をサポートするトレーニング
- 口周りの筋肉を鍛えるトレーニング
発音をスムーズにするためには、口輪筋(口の周りの筋肉)を鍛えることが重要です。
ストロー飲み:飲み物をストローで飲むことで、口の周りの筋肉を強化できます。
風船ふくらまし:風船を膨らませる動作は、発音に必要な息のコントロール力を鍛えます。 - 発音練習を行う
鏡を見ながら「さしすせそ」「たちつてと」「らりるれろ」などを発音し、舌の位置を意識させる。
歯科医院で相談すると、適切な舌の使い方を指導してもらえることもある。 - リズムに合わせた発音練習
音楽に合わせて発音練習を行うと、楽しみながら改善が可能。
例えば、「さしすせそ」をリズムに合わせて繰り返すことで、正しい発音が身につきやすくなります。
発音の問題が気になる場合は、歯科医院や言語聴覚士に相談し、適切なアドバイスを受けることも有効です。
生活習慣と口腔ケアのポイント
先天性欠如がある場合、口腔内のケアがより重要になります。欠如した歯の周囲には汚れが溜まりやすく、適切なケアを怠ると虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。
適切な歯磨き習慣を身につける
- デンタルフロスや歯間ブラシを活用する
歯の間のスペースが広くなりやすいため、通常の歯ブラシだけでは汚れを取り切れないことがあります。
デンタルフロスや歯間ブラシを使用することで、プラークの蓄積を防ぐことができます。 - フッ素入り歯磨き粉を使う
歯の欠如がある場合、残っている歯への負担が増えるため、虫歯予防がより重要になります。
フッ素入りの歯磨き粉を使用することで、歯質を強化し、虫歯を予防できます。 - 夜の仕上げ磨きを徹底する
小学生くらいまでは、親が仕上げ磨きを行い、磨き残しがないかを確認しましょう。
欠如している部分に汚れが溜まりやすいため、重点的にチェックすることが大切です。
その他の生活習慣のポイント
- 口呼吸を改善する
口呼吸の習慣がつくと、歯並びが悪くなりやすく、欠如歯の影響が大きくなります。
できるだけ鼻呼吸を意識させ、夜間の口テープなどを活用するのも有効です。 - ストレスを軽減する
先天性欠如による見た目や発音の問題で子どもがストレスを感じることもあります。
子どもが自信を持てるよう、ポジティブな声かけを心がけましょう。
適切な口腔ケアと生活習慣を整えることで、子どもが快適に過ごせる環境を作ることができます。
よくある質問Q&A

「乳歯の段階で欠如があっても大丈夫?」
乳歯の段階で歯の本数が少ない場合、親御さんは「永久歯も生えてこないのでは?」と心配になることが多いでしょう。実際に乳歯の段階で欠如があると、永久歯にも先天性欠如がある可能性が高いですが、必ずしも問題が発生するわけではありません。ここでは、乳歯の欠如に関するポイントを詳しく解説します。
乳歯の欠如と永久歯の関係
- 乳歯が生まれつきない場合、その下にある永久歯の歯胚(歯のもと)が存在しないケースが多いです。
- ただし、乳歯はあるのに永久歯だけが欠如している場合もあり、このケースでは乳歯が通常より長く残ることがあります。
乳歯の欠如がもたらす影響
- 咬み合わせの乱れ – 乳歯が少ないことで隣の歯が移動し、咬み合わせがずれることがあります。
- 顎の成長への影響 – 乳歯は顎の発達にも関係しているため、欠如があると噛む力が不均衡になり、顎の成長に偏りが出ることがあります。
- 永久歯のスペース不足 – 乳歯が少ないことで周囲の歯が寄ってしまい、永久歯が生えるスペースが不足することがあります。
対策と治療法
- 定期検診を受け、レントゲンで永久歯の状態を確認する
- 乳歯が抜ける時期を管理し、矯正治療が必要かを判断する
- 乳歯が長期間残る場合は、補助的な処置(矯正やスペース維持)を検討する
乳歯の段階で欠如が見つかった場合は、すぐに対処するのではなく、永久歯の成長と生え変わりを見ながら慎重に対応を決めることが重要です。
「放置しても問題ないケースはある?」
先天性欠如があっても、必ずしも治療が必要になるとは限りません。以下のようなケースでは、積極的な治療をせずに経過観察を行うことが可能です。
治療が不要なケース
- 親知らず(第三大臼歯)が欠如している場合
親知らずは、そもそも生えてこないことが多く、欠如していても問題になることは少ない。 - 乳歯が残っていて、正常に機能している場合
永久歯が欠如していても、乳歯がしっかり残り、噛み合わせに問題がない場合は、そのまま維持することも可能。ただし、乳歯は耐久性が低いため、長期的な管理が必要。 - 欠如が少数(1~2本)で、周囲の歯に影響を与えていない場合
欠如している歯のスペースが自然に埋まり、咬み合わせに問題がなければ、特別な治療は不要となることがある。
注意が必要なケース
- 噛み合わせがズレる場合 – 欠如したスペースに隣の歯が傾くと、噛み合わせの異常が起こる。
- 顎の成長に影響がある場合 – 特に小児期において、欠如があることで顎の発達に偏りが生じることがある。
- 発音に支障がある場合 – 前歯の欠如によってサ行やタ行が発音しづらくなることがある。
放置するかどうかの判断基準
- 歯科医師と相談し、レントゲンで永久歯の状態を確認する
- 歯の欠如による影響が小さいかどうかを評価する
- 将来的な治療の必要性を考え、治療プランを検討する
欠如の本数や位置、子どもの成長に応じて適切な判断をすることが大切です。
「矯正しない場合のデメリットは?」
先天性欠如がある場合、矯正治療を行わないことでさまざまなデメリットが生じる可能性があります。
矯正をしない場合の主なデメリット
- 歯並びが崩れる
欠如した歯のスペースに周囲の歯が倒れ込み、歯列全体が乱れる可能性が高い。 - 噛み合わせのズレが発生する
歯の欠如によって噛み合わせが不均衡になり、特定の歯に過剰な負担がかかることがある。 - 顎の成長に悪影響を与える
先天性欠如があると、顎の発育が不均衡になり、顔の歪みの原因になることがある。 - 将来的な補綴治療が困難になる
欠如した部分のスペースが狭くなり、ブリッジやインプラントの適用が難しくなる。
矯正治療を受けるメリット
- 歯列を整え、噛み合わせを改善できる
- 顎の成長を正しい方向へ促すことができる
- 口元の見た目が改善され、コンプレックスを解消できる
- 将来的な補綴治療がスムーズに進められる
矯正治療は、歯並びの美しさだけでなく、噛み合わせや顎の健康にも関わる重要な治療です。特に先天性欠如がある場合、矯正をしないことで後々の治療が難しくなることがあるため、早めに専門医と相談することをおすすめします。
まとめ:早めのチェックと適切な対応で健康な歯を育てよう

先天性欠如は珍しくないが、早めの対応が大切
先天性欠如(生まれつき歯の本数が足りない状態)は、決して珍しいものではありません。特に下顎の第二小臼歯(5番目の歯)や上顎の側切歯(2番目の前歯)に多く見られます。日本人の約10%に何らかの先天性欠如があるとされており、遺伝的な要因が関与していることも多いです。
先天性欠如の早期発見が重要な理由
- 顎の成長に影響を与えるため
乳歯が適切に生え、永久歯が正しく生え変わることで、顎の発育が促されます。しかし、欠如があると、顎の発育バランスが崩れ、咬み合わせや顔の形に影響が出る可能性があります。 - 歯並びの乱れを防ぐため
欠如した歯のスペースをそのままにしておくと、隣の歯が倒れ込んだり、噛み合わせがズレたりすることがあります。これを防ぐために、矯正治療やスペースを維持する装置の使用を検討することが重要です。 - 将来的な補綴治療の選択肢を広げるため
欠如部分を放置すると、補綴治療(インプラントやブリッジ)の選択肢が限られてしまうことがあります。早期にスペースを管理することで、最適な治療計画を立てることができます。
どのタイミングで歯科医院を受診すべき?
- 3歳児検診・5歳児検診:乳歯の本数を確認し、欠如の有無をチェック
- 6歳~12歳の混合歯列期:永久歯の生え変わりを観察し、レントゲンで歯胚の有無を確認
- 12歳以降(永久歯列完成時):最終的な治療プランを検討
先天性欠如は、早めに診断し、成長に合わせた対応を行うことが重要です。
定期検診と歯科医師との相談が最良の対策
先天性欠如があるかどうかを確認するには、定期的な歯科検診が欠かせません。
定期検診のメリット
- 欠如している歯の影響を最小限に抑えられる
欠如している歯の部分に隣の歯が移動するのを防ぎ、噛み合わせを整えることができます。 - 歯並びや咬み合わせの管理ができる
乳歯や永久歯の生え変わりを管理し、矯正治療の必要性を判断することができます。 - 将来の補綴治療の選択肢を広げられる
早い段階で治療計画を立てることで、インプラントやブリッジをより適切なタイミングで導入できます。
歯科医師と相談するときのポイント
- 欠如している歯の本数や部位を確認する
- 将来的な治療方針を相談し、矯正や補綴の必要性を判断する
- 顎の成長に合わせた治療スケジュールを検討する
先天性欠如は、適切な管理を行えば、問題なく生活することができます。そのためには、信頼できる歯科医院と連携し、継続的に診察を受けることが大切です。
子どもの健やかな成長のためにできること
先天性欠如の影響を最小限に抑え、子どもが健康な口腔環境を維持するためには、日常生活での工夫が必要です。
1. バランスの良い食事を心がける
- カルシウムやビタミンDを積極的に摂取し、顎の成長を促進する(牛乳・チーズ・魚・大豆製品)。
- よく噛む習慣をつけることで、顎の筋肉を鍛える(根菜類・海藻類など)。
2. 正しい噛み方を意識する
- 片側だけで噛まないようにする(左右バランスよく噛む)。
- 口をしっかり閉じて噛む(口呼吸を防ぎ、正しい歯並びを促す)。
3. 適切な口腔ケアを徹底する
- デンタルフロスや歯間ブラシを活用することで、欠如部分に汚れが溜まるのを防ぐ。
- 仕上げ磨きを続ける(小学生までは親が仕上げ磨きを行い、磨き残しがないか確認する)。
4. ストレスを軽減し、子どもに寄り添う
- 歯の欠如による見た目や発音の変化に不安を感じる子どももいるため、前向きな声かけを心がける。
- 「歯が少ない=特別なことではない」と理解させることで、自信を持てるようサポートする。
親が適切なサポートをすることで、子どもは安心して成長することができます。
監修:愛育クリニック麻布歯科ユニット
所在地〒:東京都港区南麻布5丁目6-8 総合母子保健センター愛育クリニック
電話番号☎:03-3473-8243
*監修者
愛育クリニック麻布歯科ユニット
ドクター 安達 英一
*出身大学
日本大学歯学部
*経歴
・日本大学歯学部付属歯科病院 勤務
・東京都式根島歯科診療所 勤務
・長崎県澤本歯科医院 勤務
・医療法人社団東杏会丸ビル歯科 勤務
・愛育クリニック麻布歯科ユニット 開設
・愛育幼稚園 校医
・愛育養護学校 校医
・青山一丁目麻布歯科 開設
・区立西麻布保育園 園医
*所属
・日本歯科医師会
・東京都歯科医師会
・東京都港区麻布赤坂歯科医師会
・日本歯周病学会
・日本小児歯科学会
・日本歯科審美学会
・日本口腔インプラント学会
カテゴリー:コラム 投稿日:2025年3月14日

